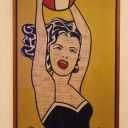大西洋を渡って両親が遊びに来たので、8月の3日間は観光に充てる。
・自由の女神
先月はスタテンアイランドフェリーから眺めただけだったが、今日はバッテリーパーク(Battery Park)から出るクルーズ船に乗って島へ上陸する。天候はあいにくの曇りだが、海上には松明を手にした銅像が凛然と立っている。海を渡ってきた多くの移民たちも、同じ光景を目にしたことだろう。彼らは何を思ったか。大きな期待を胸に、自由と希望を追い求めていたに違いない。ハドソン川の対岸にはロウアー・マンハッタンの高層ビル群が見え、中でも生まれ変わった世界貿易センタービルは一際目立つ。13年前、乗っ取った航空機を操舵して二つの摩天楼に突撃したテロリストの目にも、自由の女神が映っていたはずだ。彼らは何を思ったか。アメリカの象徴をまさに破壊せんとする異常な高揚感だっただろうか。台座の置かれた島はごく小さな面積で、あっという間に歩いて回ることができた。日本語の音声ガイドもついているのだが、ところどころ吹き替えがおかしい箇所があって笑える。そういえば、銅像の設計者バルトルディはアルザス地方コルマールの出身であった。訪れたことのある場所が知識としてつながるのはなかなか面白い。
帰りの船は移民局があったエリス(Ellis)島にも寄港するのだが、小雨が降ってきたのでそのままマンハッタンへ戻ることにした。
・ミュージカル
一日のスタートが遅かったので、気が付けば16時になっている。44丁目と9番街の交差点にあるDon Giovanniというイタリア料理屋でのんびりと早めの夕食をとった後、辺りをぶらぶらと散策してからアンバサダー劇場へ。再び『シカゴ』を観ることになった。個人的には別のものが良かったのだが、まあ仕方ない。ただ前回に比べるとだいぶ英語が聴解でき、ストーリーもある程度分かるようになったのには我ながら驚いた。ただ、急速なテンポで挟まれるちょっとしたジョークなどは未だに分からない。観客にはどっと笑いが起こるのだが、こちらは笑いどころで笑えない悲しさを噛みしめるw
写真
1・2枚目:自由の女神
3枚目:アンバサダー劇場
970文字
・自由の女神
先月はスタテンアイランドフェリーから眺めただけだったが、今日はバッテリーパーク(Battery Park)から出るクルーズ船に乗って島へ上陸する。天候はあいにくの曇りだが、海上には松明を手にした銅像が凛然と立っている。海を渡ってきた多くの移民たちも、同じ光景を目にしたことだろう。彼らは何を思ったか。大きな期待を胸に、自由と希望を追い求めていたに違いない。ハドソン川の対岸にはロウアー・マンハッタンの高層ビル群が見え、中でも生まれ変わった世界貿易センタービルは一際目立つ。13年前、乗っ取った航空機を操舵して二つの摩天楼に突撃したテロリストの目にも、自由の女神が映っていたはずだ。彼らは何を思ったか。アメリカの象徴をまさに破壊せんとする異常な高揚感だっただろうか。台座の置かれた島はごく小さな面積で、あっという間に歩いて回ることができた。日本語の音声ガイドもついているのだが、ところどころ吹き替えがおかしい箇所があって笑える。そういえば、銅像の設計者バルトルディはアルザス地方コルマールの出身であった。訪れたことのある場所が知識としてつながるのはなかなか面白い。
帰りの船は移民局があったエリス(Ellis)島にも寄港するのだが、小雨が降ってきたのでそのままマンハッタンへ戻ることにした。
・ミュージカル
一日のスタートが遅かったので、気が付けば16時になっている。44丁目と9番街の交差点にあるDon Giovanniというイタリア料理屋でのんびりと早めの夕食をとった後、辺りをぶらぶらと散策してからアンバサダー劇場へ。再び『シカゴ』を観ることになった。個人的には別のものが良かったのだが、まあ仕方ない。ただ前回に比べるとだいぶ英語が聴解でき、ストーリーもある程度分かるようになったのには我ながら驚いた。ただ、急速なテンポで挟まれるちょっとしたジョークなどは未だに分からない。観客にはどっと笑いが起こるのだが、こちらは笑いどころで笑えない悲しさを噛みしめるw
写真
1・2枚目:自由の女神
3枚目:アンバサダー劇場
970文字
・総括
長いように思われた実習もついに終わりを迎えることとなった。始まってしまえば、本当にあっという間である。率直な感想としては全てが期待通りの実習というわけではなかった。思い描いていたものと異なる現実に直面し、それを一つ一つ解決しようと苦悩の毎日を過ごしてきた。ところが、淡桃色に包まれた中世の回廊や、白で統一されたカタツムリ型の螺旋回廊にひとり佇み、異邦で暮らした7月の日々を振り返ってみても、なかなか明確なetiologyは見えてこない。英語力、医学知識、性格、思考。どれもそれなりの割合で寄与はあろう。ここで他人や環境のせいにするのは極めて安直で簡単なことだから、その方面への検索はなるべく避け、自己責任という名のetiologyを具体的な形で見出すべく努力を重ねてきた。しかし大変残念ながら、visiting student-unfriendlyという事実は客観的に認めざるを得ない。こればかりは運任せであり、自力ではどうにもならないものだった。温かな幸運に恵まれる人もいる一方で、幾多もの艱難に悶え苦しむ人もいるのだ。会った人間と過ごした環境は、異邦の印象を大きく左右する。したがって誰もが何かしらの色眼鏡をかけて故郷に帰るわけだが、どうやら自分は分厚くて暗いレンズを持って帰ることになりそうだ。
しかし、必ずしも全ての経験が薔薇色であるとは限らないし、またそうである必要もない。長い目で見れば、この一か月が今後の人生の糧となったことは間違いないと感じている。苦い経験やお会いした各先生方の話を総合的に踏まえると、いわゆる「国際的に通用する」の何たるかを身をもって感じたというのは今回の短期留学の最大の収穫だった。実力主義という言葉がぴったり当てはまるこの国でゼロからスタートし、native English speakerと同じ土俵で戦い、上を目指して行くというのは極めて険しい道のりである。その観点からすれば、異邦人として、まして実績も何もないただの学生として暮らした今回の自分は無力であったの一言に尽きるということだ。
とくに、言葉の壁が永久につきまとう。英語に自信があっても、である。「言葉は慣れだから、仕事上もだんだん問題にならなくなる」は、もちろん正しい。しかし重要なのは、どのレベルで満足と考えるかということだ。臨床医とは、言葉を巧みに操る高度なコミュニケーション技術を必要とし、時には感情の機微を解し、人間の心情の奥深くまで踏み込んだsensitiveな内容をも扱う特殊な職種である。自分は何をしても決してnative English speakerにはなり得ないのだから、その時点で圧倒的不利を強いられる。意思疎通ができれば良い、という水準では彼らと本当の勝負はできないと個人的には思うのだ。したがって同じ土俵で戦うというのなら、言葉の壁をはるかに凌駕するほどの何らかの実力、実績が求められる。
「アメリカの医療技術は世界の最先端を行っている。それに比べて日本は遅れている」と、みな口を揃えて言う。悔しいことだが、それは正しい。事実だ。しかし、「だから日本を見限ってアメリカでexcitingな最先端をやっていくことに意味がある」というのは、まあ理解できなくもないが、動機としては少々違うのではないか。日本の先進性は、先人たちの血の滲むような努力に支えられている。むしろその努力を継承し、我々が最先端となるべく先頭に立って尽力するのが使命ではないのか。「国際的に通用する」力が求められるのはまさにこの局面であり、身を置く国を問わずあらゆる物事を積極的に吸収し、然るべき場で意見を表明し、議論を戦わせていかねばならないと思っている。
・ロックフェラー・センター(Rockfeller Center)
木曜の夜はロックフェラー・センターの展望台に登る。初旬に行ったエンパイア・ステートに比べると高さは劣るが、時間指定の前売券でほとんど並ばずに入れた上に、職員もはるかに感じが良かった。さて、北側に広がるセントラルパークはマンハッタン島に敷かれた緑色の絨毯のようであり、南側には正面にどかんとエンパイア・ステート、そのさらに向こうには新生WTCの摩天楼も見える。展望デッキの設計も上手い具合にできていて、ガラスの壁が張り巡らされた中段があたかも転落防止の緩衝地帯のように機能することで、最上段は邪魔なガラスや柵のない開放的な構造となっている。夜景が狙いなので、日没を挟んだ前後2時間くらいをデッキでうろつく。刻一刻と表情を変えてゆく黄昏の空は、いつ見ても心打たれるものである。
写真
1枚目:セントラルパーク
2枚目:黄昏時
3枚目:マンハッタンの夜
2010文字
長いように思われた実習もついに終わりを迎えることとなった。始まってしまえば、本当にあっという間である。率直な感想としては全てが期待通りの実習というわけではなかった。思い描いていたものと異なる現実に直面し、それを一つ一つ解決しようと苦悩の毎日を過ごしてきた。ところが、淡桃色に包まれた中世の回廊や、白で統一されたカタツムリ型の螺旋回廊にひとり佇み、異邦で暮らした7月の日々を振り返ってみても、なかなか明確なetiologyは見えてこない。英語力、医学知識、性格、思考。どれもそれなりの割合で寄与はあろう。ここで他人や環境のせいにするのは極めて安直で簡単なことだから、その方面への検索はなるべく避け、自己責任という名のetiologyを具体的な形で見出すべく努力を重ねてきた。しかし大変残念ながら、visiting student-unfriendlyという事実は客観的に認めざるを得ない。こればかりは運任せであり、自力ではどうにもならないものだった。温かな幸運に恵まれる人もいる一方で、幾多もの艱難に悶え苦しむ人もいるのだ。会った人間と過ごした環境は、異邦の印象を大きく左右する。したがって誰もが何かしらの色眼鏡をかけて故郷に帰るわけだが、どうやら自分は分厚くて暗いレンズを持って帰ることになりそうだ。
しかし、必ずしも全ての経験が薔薇色であるとは限らないし、またそうである必要もない。長い目で見れば、この一か月が今後の人生の糧となったことは間違いないと感じている。苦い経験やお会いした各先生方の話を総合的に踏まえると、いわゆる「国際的に通用する」の何たるかを身をもって感じたというのは今回の短期留学の最大の収穫だった。実力主義という言葉がぴったり当てはまるこの国でゼロからスタートし、native English speakerと同じ土俵で戦い、上を目指して行くというのは極めて険しい道のりである。その観点からすれば、異邦人として、まして実績も何もないただの学生として暮らした今回の自分は無力であったの一言に尽きるということだ。
とくに、言葉の壁が永久につきまとう。英語に自信があっても、である。「言葉は慣れだから、仕事上もだんだん問題にならなくなる」は、もちろん正しい。しかし重要なのは、どのレベルで満足と考えるかということだ。臨床医とは、言葉を巧みに操る高度なコミュニケーション技術を必要とし、時には感情の機微を解し、人間の心情の奥深くまで踏み込んだsensitiveな内容をも扱う特殊な職種である。自分は何をしても決してnative English speakerにはなり得ないのだから、その時点で圧倒的不利を強いられる。意思疎通ができれば良い、という水準では彼らと本当の勝負はできないと個人的には思うのだ。したがって同じ土俵で戦うというのなら、言葉の壁をはるかに凌駕するほどの何らかの実力、実績が求められる。
「アメリカの医療技術は世界の最先端を行っている。それに比べて日本は遅れている」と、みな口を揃えて言う。悔しいことだが、それは正しい。事実だ。しかし、「だから日本を見限ってアメリカでexcitingな最先端をやっていくことに意味がある」というのは、まあ理解できなくもないが、動機としては少々違うのではないか。日本の先進性は、先人たちの血の滲むような努力に支えられている。むしろその努力を継承し、我々が最先端となるべく先頭に立って尽力するのが使命ではないのか。「国際的に通用する」力が求められるのはまさにこの局面であり、身を置く国を問わずあらゆる物事を積極的に吸収し、然るべき場で意見を表明し、議論を戦わせていかねばならないと思っている。
・ロックフェラー・センター(Rockfeller Center)
木曜の夜はロックフェラー・センターの展望台に登る。初旬に行ったエンパイア・ステートに比べると高さは劣るが、時間指定の前売券でほとんど並ばずに入れた上に、職員もはるかに感じが良かった。さて、北側に広がるセントラルパークはマンハッタン島に敷かれた緑色の絨毯のようであり、南側には正面にどかんとエンパイア・ステート、そのさらに向こうには新生WTCの摩天楼も見える。展望デッキの設計も上手い具合にできていて、ガラスの壁が張り巡らされた中段があたかも転落防止の緩衝地帯のように機能することで、最上段は邪魔なガラスや柵のない開放的な構造となっている。夜景が狙いなので、日没を挟んだ前後2時間くらいをデッキでうろつく。刻一刻と表情を変えてゆく黄昏の空は、いつ見ても心打たれるものである。
写真
1枚目:セントラルパーク
2枚目:黄昏時
3枚目:マンハッタンの夜
2010文字
起きたら昼前になっていた。生活の合間にQBオンラインをちまちま進めてきた結果、今日で神経、血液、アレ膠、内代の4つが終了。ノートを脇に置いて勉強するわけではないので、恐ろしいスピードで片付いていく。シャッフル機能もなかなか使えるし、後で出来なかった問題だけに取り組むこともできるという、2周目に最適なシステム。もっと早くから着手すべきだった。何事も"should have done"ばかりでは本当に見苦しいのだが、今年に入ってからとくにそれが多いのは何とも残念である。
・街歩き
夕方は散策に出かける。96丁目で急行線に乗り換えてはるばるチェンバーズ・ストリート(Chambers St.)まで南下し、トライベッカ(Tribeca)から歩き始める。映画産業の街と紹介されていたが、かなり静かな場所である。鄙びた街並みに夕刻の斜光線が差し込み、どことなく哀愁が漂う。そして北へ向かってキャナル・ストリートを越えると、4週間前も訪れたソーホーの街区である。ガイドブックに載っていたカースト・アイアン建築の建物を見て回りながら、狭い道をさまよい歩く。日没の時刻はまだ先のはずだが太陽高度はずいぶんと落ちたようで、寒い闇が路地を蝕みつつある。
北西へ歩いていくと、グリニッチ・ビレッジ(Greenwich Village)である。18~19世紀の家が立ち並ぶというベッドフォード・ストリート(Bedford St.)を歩く。レンガ造りの建物は先週末のビーコン・ヒルの景観に通じるものがある。マンハッタンの中でも、碁盤目が崩れて通りの名前が番号でないところは古い地区と見える。古いと言っても、ごく近代ではあるが。最後は、ハドソン・ストリート(Hudson St.)を北上してチェルシーまで出る。マーケットの海鮮市場が20時ぎりぎりで閉店になっていたことに落胆し、地下鉄で125丁目へ帰ったのだった。それなりに歩いた一日であった。
写真
1枚目:トライベッカ
2枚目:ソーホー
3枚目:グリニッチ・ビレッジ
886文字
・街歩き
夕方は散策に出かける。96丁目で急行線に乗り換えてはるばるチェンバーズ・ストリート(Chambers St.)まで南下し、トライベッカ(Tribeca)から歩き始める。映画産業の街と紹介されていたが、かなり静かな場所である。鄙びた街並みに夕刻の斜光線が差し込み、どことなく哀愁が漂う。そして北へ向かってキャナル・ストリートを越えると、4週間前も訪れたソーホーの街区である。ガイドブックに載っていたカースト・アイアン建築の建物を見て回りながら、狭い道をさまよい歩く。日没の時刻はまだ先のはずだが太陽高度はずいぶんと落ちたようで、寒い闇が路地を蝕みつつある。
北西へ歩いていくと、グリニッチ・ビレッジ(Greenwich Village)である。18~19世紀の家が立ち並ぶというベッドフォード・ストリート(Bedford St.)を歩く。レンガ造りの建物は先週末のビーコン・ヒルの景観に通じるものがある。マンハッタンの中でも、碁盤目が崩れて通りの名前が番号でないところは古い地区と見える。古いと言っても、ごく近代ではあるが。最後は、ハドソン・ストリート(Hudson St.)を北上してチェルシーまで出る。マーケットの海鮮市場が20時ぎりぎりで閉店になっていたことに落胆し、地下鉄で125丁目へ帰ったのだった。それなりに歩いた一日であった。
写真
1枚目:トライベッカ
2枚目:ソーホー
3枚目:グリニッチ・ビレッジ
886文字
いわゆる買い物が趣味に占める割合がかなり低いので、振り返ってみると週末の観光は美術館、博物館、景勝地、街歩きなどが中心となっている。『地球の歩き方』で70ページ以上を占めるショッピングの部分は、まるで手を付けていないw
・クロイスターズ美術館(The Cloisters)
ここはメトロポリタン美術館の分館ということになっていて、建築も含めて中世ヨーロッパの修道院の遺物が集められている。最大の見どころはクサ(Cuxa)の回廊と一角獣のタペストリー。しかし回廊は実物をフランスから運んできた後にサイズを小さくして再構成したものである。この建築はどこを切り取っても絵になるから実に写欲をそそる被写体なのだが、実際に中世からこの地にあったわけではないことを考えると、どうも映画のセットのような美しさしかないとでも言えば良いのか、表面的な装飾といった性質を拭いきれていないような印象を受ける。それでも充実したコレクションや流麗な建築に囲まれているとあたかもヨーロッパへ来たかのようであり、外の植物園も面白かった。周囲は公園として綺麗に整備されていて、ハドソン川や対岸のニュージャージーの景色も一望できる。
・グッゲンハイム(Guggenheim)美術館
86丁目でA線を降り、コロンバス・アベニュー(Columbus Ave.)にある店でビーフサンドを食べた後、バスでセントラルパークを横断してアッパー・イースト・サイド(Upper East Side)へ。午後はグッゲンハイムを訪れる。『ザ・バンク 堕ちた巨像』という映画で銃撃戦が行われていたのが妙に印象に残っているカタツムリ型の建物である。屋内は螺旋回廊をぐるぐる登る形で作品を鑑賞するという斬新な建築になっていて、このメインエリアは特別展のスペースである。Italian Futurismの展示が行われていた。1時間半ほどかけてゆっくり眺めながら頂上まで登っていく。有名どころを展示している常設展は回廊の脇のアネックスにあり、ゴッホやらゴーギャンやらは2階に集中している。
別段意図したわけではないのだが、クロイスターズといいグッゲンハイムといい、今日は回廊に縁がある一日となった。螺旋回廊の途中にあるベンチに腰掛け、しばし瞑想するのも乙なものである。ニューヨークでの生活も終盤に差し掛かってきた今、このひと月を振り返ってそろそろ考えをまとめねばなるまい。
・夏の宴
先週末のボストンでの対話が発展して、有難いことに今宵マンハッタンで開かれる宴会に招待して頂いた。ここで働くとはどういうことなのか、さらに深く考える機会である。アメリカは、なぜ世界をリードするのか。アイデンティティとは何か。将来の選択肢を増やすために、今から何をすべきか。色々と話題は尽きない。しかし、このアメ留で感銘を受けて海外での臨床を決意するかと言われると、少なくとも現時点ではそれは否である。もっと色々な考え方を知り、情報を集め、自らの思索を深めていかないことには、しばらく結論は出ないように思われる。ただ、学生という自由な立場を活かせる時間も、いくばくもなく終わってしまう。どうしようか。
二次会までお邪魔して、125丁目に帰ったら1時を回っていた。
写真
1枚目:クサの回廊
2枚目:タペストリー
3枚目:グッゲンハイム美術館
1485文字
・クロイスターズ美術館(The Cloisters)
ここはメトロポリタン美術館の分館ということになっていて、建築も含めて中世ヨーロッパの修道院の遺物が集められている。最大の見どころはクサ(Cuxa)の回廊と一角獣のタペストリー。しかし回廊は実物をフランスから運んできた後にサイズを小さくして再構成したものである。この建築はどこを切り取っても絵になるから実に写欲をそそる被写体なのだが、実際に中世からこの地にあったわけではないことを考えると、どうも映画のセットのような美しさしかないとでも言えば良いのか、表面的な装飾といった性質を拭いきれていないような印象を受ける。それでも充実したコレクションや流麗な建築に囲まれているとあたかもヨーロッパへ来たかのようであり、外の植物園も面白かった。周囲は公園として綺麗に整備されていて、ハドソン川や対岸のニュージャージーの景色も一望できる。
・グッゲンハイム(Guggenheim)美術館
86丁目でA線を降り、コロンバス・アベニュー(Columbus Ave.)にある店でビーフサンドを食べた後、バスでセントラルパークを横断してアッパー・イースト・サイド(Upper East Side)へ。午後はグッゲンハイムを訪れる。『ザ・バンク 堕ちた巨像』という映画で銃撃戦が行われていたのが妙に印象に残っているカタツムリ型の建物である。屋内は螺旋回廊をぐるぐる登る形で作品を鑑賞するという斬新な建築になっていて、このメインエリアは特別展のスペースである。Italian Futurismの展示が行われていた。1時間半ほどかけてゆっくり眺めながら頂上まで登っていく。有名どころを展示している常設展は回廊の脇のアネックスにあり、ゴッホやらゴーギャンやらは2階に集中している。
別段意図したわけではないのだが、クロイスターズといいグッゲンハイムといい、今日は回廊に縁がある一日となった。螺旋回廊の途中にあるベンチに腰掛け、しばし瞑想するのも乙なものである。ニューヨークでの生活も終盤に差し掛かってきた今、このひと月を振り返ってそろそろ考えをまとめねばなるまい。
・夏の宴
先週末のボストンでの対話が発展して、有難いことに今宵マンハッタンで開かれる宴会に招待して頂いた。ここで働くとはどういうことなのか、さらに深く考える機会である。アメリカは、なぜ世界をリードするのか。アイデンティティとは何か。将来の選択肢を増やすために、今から何をすべきか。色々と話題は尽きない。しかし、このアメ留で感銘を受けて海外での臨床を決意するかと言われると、少なくとも現時点ではそれは否である。もっと色々な考え方を知り、情報を集め、自らの思索を深めていかないことには、しばらく結論は出ないように思われる。ただ、学生という自由な立場を活かせる時間も、いくばくもなく終わってしまう。どうしようか。
二次会までお邪魔して、125丁目に帰ったら1時を回っていた。
写真
1枚目:クサの回廊
2枚目:タペストリー
3枚目:グッゲンハイム美術館
1485文字
・停滞
4週目ともなると環境に順応してくる一方、停滞も生じる。やはり感じるのは、先週も言及した「チームの一員として自分の意見や方針を表明する」段階に全く達していないということで、そこには周囲の人間や環境といった外的要因も大きく関与している一方、言葉の壁も厳然と立ちはだかっている。そういうわけで、存在感なく漠然と過ごす一週間になってしまった。あるいは、自らの努力の作用と、外的要因の力が平衡状態に達したと言っても良いかもしれない。
・言葉と思考
当たり前のことだがたいていの思考は言葉を介して行われていて、むしろ言葉が思考を支配しているといっても良い。自分の場合は日本語が極めて支配的であるから、英語との間で常に何らかの変換作業を強いられることになる。「医学分野は専門用語が多いので、用語だけでも何とか英語で話が通じる」「言い回しは決まっているので難しくはない」という意見を耳にしたことがある。むろんある程度は正しいのかもしれないが、果たして日本語で行っているのと同じレベルで議論ができているのだろうか。同等に高度な議論を外国語で行うというのがいかに難しいかを日々実感するわけである。
・プレゼン
カルテを書いたこともあり、進行性ミオクローヌスてんかんについて簡単なプレゼンをする機会を与えられた。週明けにかけて論文を読み、ハンドアウトと原稿を作る。かなり稀な疾患なので文献も少なく、それほど大変な作業ではなかった。プレゼン自体はほぼ原稿の棒読みにならざるを得ず、「書く論理で話す」という自らの理想から程遠い形になったのだが、まあそれなりに評価はされたようだ。どうやら「書く」と「話す」のバランスは、永遠の課題になりそうである。
・ハミルトン・パーク(Hamilton Park)
金曜の実習後、思い立ってニュージャージーへ夜景を撮りに行くことにした。42丁目にあるポートオーソリティ(Port Authority)バスターミナルの212番ゲートから出る128、165、166、168系統のいずれかのバスに乗り、リンカーン(Lincoln)トンネルでハドソン川をくぐってから4つ目のBoulevard East at Eldorado Plというバス停で下車すると、目的地のハミルトン・パークが目の前に現れる。このバスは完全に通期路線で、観光客の姿は見当たらない。公園自体も夜景の穴場といった感じで、暇を持て余した地元民で賑わっている。この夜景スポットは高台にあるため、林立する摩天楼を同じ高さから眺められるのが特徴。また対岸はミッドタウンにあたり、南はロウアー・マンハッタンから、北はモーニングサイド・ハイツ(Morningside Heights)に至るまで、島の全景が一望のもとである。
到着したのは19時20分頃。斜陽から日没、黄昏、そして夜の帳が下りるまで何だかんだ2時間近く居座ってしまった。早いもので、まもなく渡米してから4週間が経とうとしている。宵闇に浮かぶ無数の灯りを見ながら、苦難の日々を振り返る。
写真
1枚目:夕刻の反照
2枚目:ロウアー・マンハッタン
3枚目:ミッドタウン
1438文字
4週目ともなると環境に順応してくる一方、停滞も生じる。やはり感じるのは、先週も言及した「チームの一員として自分の意見や方針を表明する」段階に全く達していないということで、そこには周囲の人間や環境といった外的要因も大きく関与している一方、言葉の壁も厳然と立ちはだかっている。そういうわけで、存在感なく漠然と過ごす一週間になってしまった。あるいは、自らの努力の作用と、外的要因の力が平衡状態に達したと言っても良いかもしれない。
・言葉と思考
当たり前のことだがたいていの思考は言葉を介して行われていて、むしろ言葉が思考を支配しているといっても良い。自分の場合は日本語が極めて支配的であるから、英語との間で常に何らかの変換作業を強いられることになる。「医学分野は専門用語が多いので、用語だけでも何とか英語で話が通じる」「言い回しは決まっているので難しくはない」という意見を耳にしたことがある。むろんある程度は正しいのかもしれないが、果たして日本語で行っているのと同じレベルで議論ができているのだろうか。同等に高度な議論を外国語で行うというのがいかに難しいかを日々実感するわけである。
・プレゼン
カルテを書いたこともあり、進行性ミオクローヌスてんかんについて簡単なプレゼンをする機会を与えられた。週明けにかけて論文を読み、ハンドアウトと原稿を作る。かなり稀な疾患なので文献も少なく、それほど大変な作業ではなかった。プレゼン自体はほぼ原稿の棒読みにならざるを得ず、「書く論理で話す」という自らの理想から程遠い形になったのだが、まあそれなりに評価はされたようだ。どうやら「書く」と「話す」のバランスは、永遠の課題になりそうである。
・ハミルトン・パーク(Hamilton Park)
金曜の実習後、思い立ってニュージャージーへ夜景を撮りに行くことにした。42丁目にあるポートオーソリティ(Port Authority)バスターミナルの212番ゲートから出る128、165、166、168系統のいずれかのバスに乗り、リンカーン(Lincoln)トンネルでハドソン川をくぐってから4つ目のBoulevard East at Eldorado Plというバス停で下車すると、目的地のハミルトン・パークが目の前に現れる。このバスは完全に通期路線で、観光客の姿は見当たらない。公園自体も夜景の穴場といった感じで、暇を持て余した地元民で賑わっている。この夜景スポットは高台にあるため、林立する摩天楼を同じ高さから眺められるのが特徴。また対岸はミッドタウンにあたり、南はロウアー・マンハッタンから、北はモーニングサイド・ハイツ(Morningside Heights)に至るまで、島の全景が一望のもとである。
到着したのは19時20分頃。斜陽から日没、黄昏、そして夜の帳が下りるまで何だかんだ2時間近く居座ってしまった。早いもので、まもなく渡米してから4週間が経とうとしている。宵闇に浮かぶ無数の灯りを見ながら、苦難の日々を振り返る。
写真
1枚目:夕刻の反照
2枚目:ロウアー・マンハッタン
3枚目:ミッドタウン
1438文字
ボストンの週末 その2
2014年7月20日 留学
旅先で迎える朝は、すがすがしい。朝食のパンを食べてココアを飲みながら、各方面へのメールを返して雑務を終える。
・フリーダム・トレイル(Freedom Trail)
大した下調べもしないままこの街に来てしまったのだが、とりあえずフリーダム・トレイルという、ボストンの16の歴史的名所を回ることができるモデルコースを歩くことにした。ボストン・コモン(Boston Common)のビジターセンター前がスタート地点で、ルートにあたる街路や小径には赤い線が引かれている。この線をたどって行けば、効率的に名所を巡れるという仕組みである。中2の秋だったか、『物語アメリカの歴史』という中公新書が社会の教材になっていた気がするが、たとえばこの本を渡米前に読んでおけばボストン観光は数段面白かったかもしれない。地図には色々と名所の解説が書いてあるのだが、「サミュエル・アダムズ(Samuel Adams)って誰だよ・・・」というレベルの背景知識だったので、全てが「へえー」で終わってしまったのが残念であった。どうでも良いが、彼と同じ名前のボストン産ビールはなかなか美味しい。むろん、レンガ造りの古い街並みを眺めながらぶらぶらと歩き、ファインダーを覗くだけでも十分楽しい時間である。
週末ということもあってか、街にはそれなりの人で賑わっている。アメリカでも有数の古い街とあって、国内の観光客と思しき人が多いのは面白い。極端な例えかもしれないが、日本で言えば京都や奈良へ観光に来ているような感覚なのだろう。16か所を律儀に回り、最後はバンカー・ヒル(Bunker Hill)のモニュメントでゴール。気が付けば13時を過ぎ、出発から4時間弱が経過していた。
・午後
ボストンの見どころはだいたい徒歩圏内に凝縮しているので、再び歩いてチャールズ(Charles)川を渡り、市の中心部に戻る。ファニエル・ホール(Faneuil Hall)のそばにあるマーケットでそれなりにボリュームのあるチキンサンドを食べた後、昼下がりはMGHへ向かう。昨日案内して頂いた病院のギフトショップでグッズを買い、エーテル・ドームの入っている建物の外観を撮りつつ前庭でまったりして時間を過ごす。その後は地下鉄を使ってボストン美術館へも足を伸ばしたのだが、1時間強しか残されていないのに入館料の$23は割に合わないと思い、観覧は断念した。木陰のベンチに座って、ぼけーっと過ごすのも良いものである。
・帰路
サウス駅を17時10分に出るアセラ・エクスプレス(Acela Express)でボストンを去る。切符はなんと往路のNortheast Regionalの倍額以上するのだが、4時間15分の所要が3時間半に縮まるだけなので、値段に見合う速達性かと言われると微妙なところである。それに新幹線やTGVのように専用線を持っているわけでもないので、ニューヨークが近くなってくると通勤列車と共用の線路でノロノロと走る。座席は全てビジネスクラス以上の設定なのでそこは快適なのだが、それでも一回乗れば十分といったところか。まあ明日からは再び日常が待っているので、なるべく早くマンハッタンに帰るに越したことはない。
ミスティックからオールド・セイブルックまではしばしば車窓に大西洋が現れる。アセラは海岸線を猛然と駆け抜けてこの辺りの小駅をみな飛ばしてしまうのだが、厚い雲間から時おり差し込む夕刻の斜光線に照らされながら、船の群れで埋め尽くされた幾多ものハーバーが眼前を通り過ぎて行く。そして、ニューヨークへ着く頃にちょうど日没となる。夜の帳の下りた34丁目のコリアンタウンでひとり夕食をとった後、今や住み慣れた125丁目の居室へと無事に帰還したのだった。
写真
1枚目:ファニエル・ホールとサミュエル・アダムズ像
2枚目:コップスヒル(Copp’s Hill)墓地
3枚目:ミスティックの車窓
1721文字
・フリーダム・トレイル(Freedom Trail)
大した下調べもしないままこの街に来てしまったのだが、とりあえずフリーダム・トレイルという、ボストンの16の歴史的名所を回ることができるモデルコースを歩くことにした。ボストン・コモン(Boston Common)のビジターセンター前がスタート地点で、ルートにあたる街路や小径には赤い線が引かれている。この線をたどって行けば、効率的に名所を巡れるという仕組みである。中2の秋だったか、『物語アメリカの歴史』という中公新書が社会の教材になっていた気がするが、たとえばこの本を渡米前に読んでおけばボストン観光は数段面白かったかもしれない。地図には色々と名所の解説が書いてあるのだが、「サミュエル・アダムズ(Samuel Adams)って誰だよ・・・」というレベルの背景知識だったので、全てが「へえー」で終わってしまったのが残念であった。どうでも良いが、彼と同じ名前のボストン産ビールはなかなか美味しい。むろん、レンガ造りの古い街並みを眺めながらぶらぶらと歩き、ファインダーを覗くだけでも十分楽しい時間である。
週末ということもあってか、街にはそれなりの人で賑わっている。アメリカでも有数の古い街とあって、国内の観光客と思しき人が多いのは面白い。極端な例えかもしれないが、日本で言えば京都や奈良へ観光に来ているような感覚なのだろう。16か所を律儀に回り、最後はバンカー・ヒル(Bunker Hill)のモニュメントでゴール。気が付けば13時を過ぎ、出発から4時間弱が経過していた。
・午後
ボストンの見どころはだいたい徒歩圏内に凝縮しているので、再び歩いてチャールズ(Charles)川を渡り、市の中心部に戻る。ファニエル・ホール(Faneuil Hall)のそばにあるマーケットでそれなりにボリュームのあるチキンサンドを食べた後、昼下がりはMGHへ向かう。昨日案内して頂いた病院のギフトショップでグッズを買い、エーテル・ドームの入っている建物の外観を撮りつつ前庭でまったりして時間を過ごす。その後は地下鉄を使ってボストン美術館へも足を伸ばしたのだが、1時間強しか残されていないのに入館料の$23は割に合わないと思い、観覧は断念した。木陰のベンチに座って、ぼけーっと過ごすのも良いものである。
・帰路
サウス駅を17時10分に出るアセラ・エクスプレス(Acela Express)でボストンを去る。切符はなんと往路のNortheast Regionalの倍額以上するのだが、4時間15分の所要が3時間半に縮まるだけなので、値段に見合う速達性かと言われると微妙なところである。それに新幹線やTGVのように専用線を持っているわけでもないので、ニューヨークが近くなってくると通勤列車と共用の線路でノロノロと走る。座席は全てビジネスクラス以上の設定なのでそこは快適なのだが、それでも一回乗れば十分といったところか。まあ明日からは再び日常が待っているので、なるべく早くマンハッタンに帰るに越したことはない。
ミスティックからオールド・セイブルックまではしばしば車窓に大西洋が現れる。アセラは海岸線を猛然と駆け抜けてこの辺りの小駅をみな飛ばしてしまうのだが、厚い雲間から時おり差し込む夕刻の斜光線に照らされながら、船の群れで埋め尽くされた幾多ものハーバーが眼前を通り過ぎて行く。そして、ニューヨークへ着く頃にちょうど日没となる。夜の帳の下りた34丁目のコリアンタウンでひとり夕食をとった後、今や住み慣れた125丁目の居室へと無事に帰還したのだった。
写真
1枚目:ファニエル・ホールとサミュエル・アダムズ像
2枚目:コップスヒル(Copp’s Hill)墓地
3枚目:ミスティックの車窓
1721文字
ボストンの週末 その1
2014年7月19日 留学
・北東回廊
全くの奇遇だったが、小児科ポリクリの抄読会発表でお世話になったツテでこちらの先生を紹介して頂いた。先輩にお目にかかるのが半分、それにせっかくなので観光も半分ということで、この週末のボストン行きを手配したのだった。ボストンまでは鉄道、航空機、バスの選択肢があるが、空路は空港の往復やら搭乗手続きやらが面倒だし、アメリカに来てまでだらだらバスに乗るのも悲しいので、ここはやはりアムトラック(Amtrak)の列車を選ぶ。ペン・ステーションを7時ちょうどに出る150列車に乗り込んだ。始発は午前3時頃のワシントンDC(Washington DC)なので、既に乗客がちらほら。この路線はNortheast Corridor(邦訳:北東回廊)と呼ばれる東海岸の大幹線で、列車はワシントンDCからボストンまでの700km以上を通しで走破することになる。種別はNortheast Regionalというもので、言ってみれば都市間を結ぶ急行列車のような感じである。アメリカの鉄道もヨーロッパと同じく集中動力方式で、電気機関車が先頭に立つ。ステンレスボディが印象的な客車は航空機のようにかなり丸みを帯びた造形で面白い。車内は自由席でどこに座っても良いことになっているが、座席の枠は限られている。いっそ指定席にしてくれた方がありがたい。車内にはWiFiが通っていてなかなか便利である。
特筆すべき車窓は、オールド・セイブルック(Old Saybrook)を出てコネチカット(Conneticut)川を渡るところ、その先の湿地帯を抜けてニアンティック(Niantic)湾の砂浜をなぞるところ、港町ニューロンドン(New London)の風景、そこからミスティック(Mystic)まで至るところに点在するハーバーなどなど。GoogleマップとGPSを片手に車窓を眺めれば、鉄道旅行は数段面白くなるw ペン・ステーションを出て4時間15分、列車は意外にも定刻でボストン・サウス(Boston South)駅に到着したのだった。
・対話と思索
正午に無事に落ち合い、まずはボストンのオリエンテーションについてお話頂き、そしてMGH(Massachusetts General Hospital)やロングウッド・メディカル・エリア(Longwood Medical Area)を案内して下さった。1846年に「世界最初」の麻酔手術が行われたエーテル・ドーム(Ether Dome)は圧巻。病院最古の棟の4階にある。公開手術が行われたこの階段教室は今も現役で、普通にカンファなどで使われているらしい。昼食はプルデンシャル(Prudential)の近くにあるレストランにてシーフード。ボストン名物のクラムチャウダーとロブスターを頂く。何から何までお世話になり、感謝の極みである。こうして色々な話を聞いて見識を広める経験は、今後も大切にしていかねばならない。早いものでアメリカに来て3週間になるが、良いところも悪いところも徐々に見えてきたように思う。果たして海外で働くとはどういうものなのか、もう少し深く考えてみたいところである。
・逍遥
16時半頃にお別れした後は、宿までぶらぶらと歩きながら帰ることにした。それなりに距離はあるのだが、知らない街は歩いているだけでも楽しい。全体的にニューヨークよりも綺麗で、とくに地下鉄と路面電車ははるかに清潔である。むしろ、ニューヨークが汚すぎるのかもしれないw 天候は曇り。美しい公園の木陰には涼しい空気が漂う。また、建物は古いレンガ造りのものが良く保存されている。とくにビーコン・ヒル(Beacon Hill)はボストンでも最も古い街区で、坂道や石畳の路地、夕刻にともるガス灯など、なかなか趣がある。随所に歴史が詰まっているような印象を受けた。
宿はJohn Jeffries Houseという、これまた趣深い歴史的建造物。ここも紹介によって知ったのだった。チャールズ/MGH(Charles/MGH)駅の目の前にあり、ホテルの値段が異様に高いボストンにありながら、比較的に廉価である。チェックインした後、カメラを片手に黄昏のビーコン・ヒルを再び歩く。ちょっとした路地に入れば、あたかもタイムスリップしたかのようである。目にとまったPanificioというビストロに入ってボストンのビール、Samuel Adamsを飲みながら、サーモンのソテーを食べた。
写真
1枚目:旅立ち
2枚目:エーテル・ドーム
3枚目:エイコーン・ストリート(Acorn Street)
1995文字
全くの奇遇だったが、小児科ポリクリの抄読会発表でお世話になったツテでこちらの先生を紹介して頂いた。先輩にお目にかかるのが半分、それにせっかくなので観光も半分ということで、この週末のボストン行きを手配したのだった。ボストンまでは鉄道、航空機、バスの選択肢があるが、空路は空港の往復やら搭乗手続きやらが面倒だし、アメリカに来てまでだらだらバスに乗るのも悲しいので、ここはやはりアムトラック(Amtrak)の列車を選ぶ。ペン・ステーションを7時ちょうどに出る150列車に乗り込んだ。始発は午前3時頃のワシントンDC(Washington DC)なので、既に乗客がちらほら。この路線はNortheast Corridor(邦訳:北東回廊)と呼ばれる東海岸の大幹線で、列車はワシントンDCからボストンまでの700km以上を通しで走破することになる。種別はNortheast Regionalというもので、言ってみれば都市間を結ぶ急行列車のような感じである。アメリカの鉄道もヨーロッパと同じく集中動力方式で、電気機関車が先頭に立つ。ステンレスボディが印象的な客車は航空機のようにかなり丸みを帯びた造形で面白い。車内は自由席でどこに座っても良いことになっているが、座席の枠は限られている。いっそ指定席にしてくれた方がありがたい。車内にはWiFiが通っていてなかなか便利である。
特筆すべき車窓は、オールド・セイブルック(Old Saybrook)を出てコネチカット(Conneticut)川を渡るところ、その先の湿地帯を抜けてニアンティック(Niantic)湾の砂浜をなぞるところ、港町ニューロンドン(New London)の風景、そこからミスティック(Mystic)まで至るところに点在するハーバーなどなど。GoogleマップとGPSを片手に車窓を眺めれば、鉄道旅行は数段面白くなるw ペン・ステーションを出て4時間15分、列車は意外にも定刻でボストン・サウス(Boston South)駅に到着したのだった。
・対話と思索
正午に無事に落ち合い、まずはボストンのオリエンテーションについてお話頂き、そしてMGH(Massachusetts General Hospital)やロングウッド・メディカル・エリア(Longwood Medical Area)を案内して下さった。1846年に「世界最初」の麻酔手術が行われたエーテル・ドーム(Ether Dome)は圧巻。病院最古の棟の4階にある。公開手術が行われたこの階段教室は今も現役で、普通にカンファなどで使われているらしい。昼食はプルデンシャル(Prudential)の近くにあるレストランにてシーフード。ボストン名物のクラムチャウダーとロブスターを頂く。何から何までお世話になり、感謝の極みである。こうして色々な話を聞いて見識を広める経験は、今後も大切にしていかねばならない。早いものでアメリカに来て3週間になるが、良いところも悪いところも徐々に見えてきたように思う。果たして海外で働くとはどういうものなのか、もう少し深く考えてみたいところである。
・逍遥
16時半頃にお別れした後は、宿までぶらぶらと歩きながら帰ることにした。それなりに距離はあるのだが、知らない街は歩いているだけでも楽しい。全体的にニューヨークよりも綺麗で、とくに地下鉄と路面電車ははるかに清潔である。むしろ、ニューヨークが汚すぎるのかもしれないw 天候は曇り。美しい公園の木陰には涼しい空気が漂う。また、建物は古いレンガ造りのものが良く保存されている。とくにビーコン・ヒル(Beacon Hill)はボストンでも最も古い街区で、坂道や石畳の路地、夕刻にともるガス灯など、なかなか趣がある。随所に歴史が詰まっているような印象を受けた。
宿はJohn Jeffries Houseという、これまた趣深い歴史的建造物。ここも紹介によって知ったのだった。チャールズ/MGH(Charles/MGH)駅の目の前にあり、ホテルの値段が異様に高いボストンにありながら、比較的に廉価である。チェックインした後、カメラを片手に黄昏のビーコン・ヒルを再び歩く。ちょっとした路地に入れば、あたかもタイムスリップしたかのようである。目にとまったPanificioというビストロに入ってボストンのビール、Samuel Adamsを飲みながら、サーモンのソテーを食べた。
写真
1枚目:旅立ち
2枚目:エーテル・ドーム
3枚目:エイコーン・ストリート(Acorn Street)
1995文字
・日々漸進
3週目ともなるとずいぶん慣れてくる。どのように過ごすのが最も有意義なのか、だんだん分かってきたように思う。同僚の留学生、当地の医学生との関係も良好。そして今週から登場したレジデントの長はそれなりに良い人で、留学生もちゃんと気にかけてくれる。大幅に環境が改善した感。そして先週の後半と同様、診察とカルテに挑む。しかしながら、やっていることはレジデントの真似事の域を出ない。身体所見はともかく、A/P、とくに治療薬の選択については全く無力。チームの一員として自分の意見や方針を表明するという段階には程遠い。まあ、日本のポリクリでやっていなかったことを、いきなりこっちでやるというのは無茶な話なのかもしれない。確か循環器内科は先の「チームの一員として…」という到達目標を提示していたような覚えがあるが、一体どれだけの学生がそれを達成しているのだろう。少なくとも自分はできなかったが、それはポリクリに対する考えが甘すぎたということなのだろうか。まあ何にせよ、よっぽど特殊な場合を除いては、日本語でさえできなかったことが、英語でできるとは考えにくい。全病棟患者を把握し、それぞれのA/Pについて十分理解していたことがこれまであったか。しかし今は同じことを英語でやろうとしているわけなので、正直なところ回診のスピーディーな議論についていくだけで精一杯である。しかしこういう経験が糧になると信じて、毎日速い英語に耳をそば立てているわけだ。
・小児神経とは
脳腫瘍とかSMAが見られるのかと思いきや、主訴の大半はseizureで、どこもかしこもseizure。したがって、議論の大半はてんかんの症候学・病因論、抗てんかん薬の使用、それに脳波の読図。神経内科のレジデントも「てんかん発作以外の患者は入って来ないのか?」と半ば嘆いていたw 一方で、内科の症例発表やクルズスもスケジュールに組み込まれており参加することになっている。morning reportと称する発表会は実に興味深い内容で、小出しにされる病歴や身体所見、検査値や画像をもとに鑑別診断を考えていく。両下肢の筋痛と歩行困難、左三叉神経麻痺、右顔面神経麻痺。答えはライム病。レジデントを対象とした神経診察のクルズスも面白い内容であった。神経といえばこういうのを期待していたのだが、小児神経は全くの別物。しかしてんかんや脳波も考えようによっては深い未知の領域で、金曜に大教室で開かれた研究の講義などは興味をそそられるものであった。どの分野にも概ね当てはまることかもしれないが、科学的な関心と臨床的な面白味はしばしばかけ離れたところにある。
・英語
回診で言っていることの半分くらいは分かるようになってきたか。一番聴解しやすいのは、アテンディングが患者家族へ行う説明。ただ、日常的にぱっぱっと交わされる速い会話は回診の議論以上に聴き取りにくい。しかも自分の返答は遅く、しどろもどろで要領を得ない。やはり、書く論理と話す論理は全くの別物であることを改めて実感する。書ければ話せるというわけではないし、読めれば聴けるというわけでもない。まあ、日本語でも会話やプレゼンがお世辞にも上手いとはいえないことを考えれば、日本語以上にoralな側面が強い英語ではさらにその辺りが際立つのかもしれない。単純なものに限って言えば会話は一種の反射みたいなもので、いかに多くの音のレパートリーを即座に操れるかということになるのだと思う。その過程に、読解や作文という要素が介在していてはいけないのだ。
今週の昼食はほぼ全てタダ飯であったw 金曜の夜は前に行った韓国料理屋でビビンバを食べながら、ささやかにビールを飲む。
写真
1枚目:『星月夜』
2枚目:アラスカグマ
3枚目:トランジット・ミュージアム
1670文字
3週目ともなるとずいぶん慣れてくる。どのように過ごすのが最も有意義なのか、だんだん分かってきたように思う。同僚の留学生、当地の医学生との関係も良好。そして今週から登場したレジデントの長はそれなりに良い人で、留学生もちゃんと気にかけてくれる。大幅に環境が改善した感。そして先週の後半と同様、診察とカルテに挑む。しかしながら、やっていることはレジデントの真似事の域を出ない。身体所見はともかく、A/P、とくに治療薬の選択については全く無力。チームの一員として自分の意見や方針を表明するという段階には程遠い。まあ、日本のポリクリでやっていなかったことを、いきなりこっちでやるというのは無茶な話なのかもしれない。確か循環器内科は先の「チームの一員として…」という到達目標を提示していたような覚えがあるが、一体どれだけの学生がそれを達成しているのだろう。少なくとも自分はできなかったが、それはポリクリに対する考えが甘すぎたということなのだろうか。まあ何にせよ、よっぽど特殊な場合を除いては、日本語でさえできなかったことが、英語でできるとは考えにくい。全病棟患者を把握し、それぞれのA/Pについて十分理解していたことがこれまであったか。しかし今は同じことを英語でやろうとしているわけなので、正直なところ回診のスピーディーな議論についていくだけで精一杯である。しかしこういう経験が糧になると信じて、毎日速い英語に耳をそば立てているわけだ。
・小児神経とは
脳腫瘍とかSMAが見られるのかと思いきや、主訴の大半はseizureで、どこもかしこもseizure。したがって、議論の大半はてんかんの症候学・病因論、抗てんかん薬の使用、それに脳波の読図。神経内科のレジデントも「てんかん発作以外の患者は入って来ないのか?」と半ば嘆いていたw 一方で、内科の症例発表やクルズスもスケジュールに組み込まれており参加することになっている。morning reportと称する発表会は実に興味深い内容で、小出しにされる病歴や身体所見、検査値や画像をもとに鑑別診断を考えていく。両下肢の筋痛と歩行困難、左三叉神経麻痺、右顔面神経麻痺。答えはライム病。レジデントを対象とした神経診察のクルズスも面白い内容であった。神経といえばこういうのを期待していたのだが、小児神経は全くの別物。しかしてんかんや脳波も考えようによっては深い未知の領域で、金曜に大教室で開かれた研究の講義などは興味をそそられるものであった。どの分野にも概ね当てはまることかもしれないが、科学的な関心と臨床的な面白味はしばしばかけ離れたところにある。
・英語
回診で言っていることの半分くらいは分かるようになってきたか。一番聴解しやすいのは、アテンディングが患者家族へ行う説明。ただ、日常的にぱっぱっと交わされる速い会話は回診の議論以上に聴き取りにくい。しかも自分の返答は遅く、しどろもどろで要領を得ない。やはり、書く論理と話す論理は全くの別物であることを改めて実感する。書ければ話せるというわけではないし、読めれば聴けるというわけでもない。まあ、日本語でも会話やプレゼンがお世辞にも上手いとはいえないことを考えれば、日本語以上にoralな側面が強い英語ではさらにその辺りが際立つのかもしれない。単純なものに限って言えば会話は一種の反射みたいなもので、いかに多くの音のレパートリーを即座に操れるかということになるのだと思う。その過程に、読解や作文という要素が介在していてはいけないのだ。
今週の昼食はほぼ全てタダ飯であったw 金曜の夜は前に行った韓国料理屋でビビンバを食べながら、ささやかにビールを飲む。
写真
1枚目:『星月夜』
2枚目:アラスカグマ
3枚目:トランジット・ミュージアム
1670文字
ちょうど小児神経なので、神経のQBをオンラインでバリバリと解き進める。しかし1周目を終えたのが1年以上前なので、もはや何も覚えていない。当時間違えた問題はきっと今でもだいたい間違えているのだろうし、合っていた問題も全て正解しているのかは怪しい。それにしても今更になって、オンラインの便利さに気が付く。これなら、6月の空き時間にいくらでも進められたはずなのだが・・・
・アメリカ自然史博物館(American Museum of Natural History)
昼前から観光に出かける。116丁目にあるコロンビア大学のキャンパスを適当に散策した後、72丁目まで下る。東へ歩を進めてセントラルパークの入口にあるダコタ・アパート(Dakota Apartments)を見てから、81丁目の自然史博物館へ。ここでは動植物、恐竜、宇宙について壮大な展示がなされていて、上野の国立科学博物館を巨大にした感じである。とくに各動物の剥製を展示したジオラマは実に良く出来ていて、背景画も含め細部まで作り込まれているのが素晴らしい。格好の被写体として写真を撮っても良いし、脇に書いてある説明をマニアックに読んでも楽しめる。アラスカグマは強烈な印象。こういう猛獣に遭遇したらたぶん死ぬしかないのだろう・・・
海洋生物は模型のみだが、如何せん展示が壮大なので見て歩くだけでも十分すぎるくらいである。宇宙科学や地学のコーナーも充実している。最後に4階の恐竜の化石を見に行く。このフロアはとくに人気であった。博物館のコレクションは量、質ともに圧倒的で、とても一日では全てを味わい尽くせない。アトラクションのような感覚で訪れても面白いし、一つ一つじっくり見て回ってもさらに深い世界に入り込めることと思う。
・トランジット・ミュージアム(Transit Museum)
夕方はブルックリンまで足を伸ばし、トランジット・ミュージアムへ。ガイドブックにはごく小さく紹介されているのみ。ここはコート・ストリート(Court St.)という廃駅を改装してオープンした地下鉄とバスの博物館で、地下鉄の階段がそのまま入口になっている。構内の線路は営業路線と連続していて、第三軌条は通電しているらしい。ここは小さな子供が多かった。最初から真面目に展示を見ていくとニューヨーク地下鉄の歴史が良く分かって実に興味深い。たいていの古い路線はアベニューに塹壕を掘った後に上から蓋をかぶせた形になっていることを知る。それと、イースト・リバーの下をくぐるトンネルは相当な難工事だったようだ。
地下2階はコート・ストリート駅の1面2線の遺構がそのままになっていて、多くの古い車両が展示されている。映画のセットのようだと思ったら、調べてみると実際に使われたこともあるようだ。車内は広告や路線図も当時のままに保存されていて、乗り込んで座っているだけでも楽しい。たくさんの家族連れに交じって当地の鉄ヲタと思しき人も熱心に写真を撮っていたのだが、「貫通扉のところへ行くから正面から写真を撮って欲しい。ここは子供が多いし家族連れには頼みにくくて・・・」と話しかけてきたw 博物館というのはいくらでもマニアックに過ごせる場所で、一つ一つの解説をじっくり読むのも乙なものである。あっという間に閉館時刻になってしまった。構内の案内表示と路線図がプリントされた黒地のTシャツを記念に買って帰る。
そういえば毎日使っていると「まあこんなもんか」という感じですっかり慣れてしまうのだが、ニューヨークの地下鉄の汚さは異常である。軌道はゴミで埋め尽くされ、駅施設の環境や衛生も劣悪といえば劣悪。また時刻表は存在せず定時性はめちゃくちゃで、たまに間隔調整と称して緩行線の電車が勝手に駅を飛ばしたりする。日本の地下鉄がいかに綺麗か、それに他社線との直通運転までこなす緻密なダイヤがいかに洗練されているかを思い知るわけだが、新天地に街を造りトンネルを掘り鉄路を敷いた偉大なる先人たちの努力に加えて、均一価格でどこまでも行ける利便性とか、24時間365日の運行で市民の足として間違いなく機能していることとかを考えれば、この無骨なニューヨークの地下鉄にも不意に畏敬の念と一種の愛着が湧いてくるのである。
写真
1枚目:海洋生物
2枚目:ティラノサウルス
3枚目:トランジット・ミュージアム
1871文字
・アメリカ自然史博物館(American Museum of Natural History)
昼前から観光に出かける。116丁目にあるコロンビア大学のキャンパスを適当に散策した後、72丁目まで下る。東へ歩を進めてセントラルパークの入口にあるダコタ・アパート(Dakota Apartments)を見てから、81丁目の自然史博物館へ。ここでは動植物、恐竜、宇宙について壮大な展示がなされていて、上野の国立科学博物館を巨大にした感じである。とくに各動物の剥製を展示したジオラマは実に良く出来ていて、背景画も含め細部まで作り込まれているのが素晴らしい。格好の被写体として写真を撮っても良いし、脇に書いてある説明をマニアックに読んでも楽しめる。アラスカグマは強烈な印象。こういう猛獣に遭遇したらたぶん死ぬしかないのだろう・・・
海洋生物は模型のみだが、如何せん展示が壮大なので見て歩くだけでも十分すぎるくらいである。宇宙科学や地学のコーナーも充実している。最後に4階の恐竜の化石を見に行く。このフロアはとくに人気であった。博物館のコレクションは量、質ともに圧倒的で、とても一日では全てを味わい尽くせない。アトラクションのような感覚で訪れても面白いし、一つ一つじっくり見て回ってもさらに深い世界に入り込めることと思う。
・トランジット・ミュージアム(Transit Museum)
夕方はブルックリンまで足を伸ばし、トランジット・ミュージアムへ。ガイドブックにはごく小さく紹介されているのみ。ここはコート・ストリート(Court St.)という廃駅を改装してオープンした地下鉄とバスの博物館で、地下鉄の階段がそのまま入口になっている。構内の線路は営業路線と連続していて、第三軌条は通電しているらしい。ここは小さな子供が多かった。最初から真面目に展示を見ていくとニューヨーク地下鉄の歴史が良く分かって実に興味深い。たいていの古い路線はアベニューに塹壕を掘った後に上から蓋をかぶせた形になっていることを知る。それと、イースト・リバーの下をくぐるトンネルは相当な難工事だったようだ。
地下2階はコート・ストリート駅の1面2線の遺構がそのままになっていて、多くの古い車両が展示されている。映画のセットのようだと思ったら、調べてみると実際に使われたこともあるようだ。車内は広告や路線図も当時のままに保存されていて、乗り込んで座っているだけでも楽しい。たくさんの家族連れに交じって当地の鉄ヲタと思しき人も熱心に写真を撮っていたのだが、「貫通扉のところへ行くから正面から写真を撮って欲しい。ここは子供が多いし家族連れには頼みにくくて・・・」と話しかけてきたw 博物館というのはいくらでもマニアックに過ごせる場所で、一つ一つの解説をじっくり読むのも乙なものである。あっという間に閉館時刻になってしまった。構内の案内表示と路線図がプリントされた黒地のTシャツを記念に買って帰る。
そういえば毎日使っていると「まあこんなもんか」という感じですっかり慣れてしまうのだが、ニューヨークの地下鉄の汚さは異常である。軌道はゴミで埋め尽くされ、駅施設の環境や衛生も劣悪といえば劣悪。また時刻表は存在せず定時性はめちゃくちゃで、たまに間隔調整と称して緩行線の電車が勝手に駅を飛ばしたりする。日本の地下鉄がいかに綺麗か、それに他社線との直通運転までこなす緻密なダイヤがいかに洗練されているかを思い知るわけだが、新天地に街を造りトンネルを掘り鉄路を敷いた偉大なる先人たちの努力に加えて、均一価格でどこまでも行ける利便性とか、24時間365日の運行で市民の足として間違いなく機能していることとかを考えれば、この無骨なニューヨークの地下鉄にも不意に畏敬の念と一種の愛着が湧いてくるのである。
写真
1枚目:海洋生物
2枚目:ティラノサウルス
3枚目:トランジット・ミュージアム
1871文字
心安らぐ週末が訪れる。そういえば、もう40日くらい国試勉強に着手していない。帰国後は比較的すぐにマッチングも控えていることだし、空き時間にQBオンラインで2周目も進めておこう。しかしせっかくニューヨークに来ているので、休日は出かけないともったいない。生活・勉強と観光を上手く切り替えながら両立するのが7月の課題となろう。
・MoMA(Museum of Modern Art)
今日はニューヨーク近代美術館、通称MoMAへ足を運ぶ。セントラルパークからさほど離れていないミッドタウン(Midtown)にある。学生証を見せたらどういうわけかタダ券をもらえたw 主に4階と5階の常設展を見て回る。モネの睡蓮、ゴッホの星月夜、それにリキテンスタイン(Lichtenstein)やウォーホル(Warhol)といった有名どころをチェックしながら歩を進める。いつもデュプロの「★」を拾いながら鑑賞するような形になるのは仕方ない。そういえば、星月夜に描かれた渦巻きはメニエール病の回転性めまいを表現したものだという説があるらしい。近代美術とあって全体的にかなり斬新な作品が多く、解説を聞くとさらに面白い。また格式ばった古典的な感じがなく、見ていても肩が凝らないとでも言えば良いのか、ごく自然な感覚で作品を鑑賞できるのが良かった。
しかし落書きにしか見えない絵や、全く訳の分からないオブジェもたくさんあって、たとえ意味付けがあっても一見して全く意味不明なものにどういう「意味」があるのか、という疑問は払拭されないままである。作品それ自体もさることながら、文脈まで含めた包括的なものに対しても目を向けないことには、これらは結局いつまでも分からない。してみると、いわゆる傑作が傑作たるゆえんは何なのかと、いつも不思議に思うわけだ。傑作という意見で多数が合意するから傑作たりえるのか、それとも絶対的な何かが内包されているのか。評価は他人が下すものなので、これはいつも難しい問題だと思っている。まあ、単に自分の勉強不足といえばそれまでかもしれない。
・散策
3時間弱の滞在の後、51丁目から23丁目まで6号線で移動。まずはグラマシー(Gramacy)を歩く。ガイドブックには歴史的建造物が多いとあったが、そこまで古い印象は受けない。壁のようなフラットアイアン・ビル(Flatiron Building)や、木陰にひっそりと佇むセオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)の生家を眺めつつ、ユニオン・スクエア(Union Square)まで南下する。4番街は歩行者天国になっていて、道路の両脇には無数の露店や屋台。この辺りまで来るとイースト・ビレッジ(East Village)という地区になり、色々な移民の街である。8丁目を東に歩くと日本の居酒屋やラーメン屋も散見される。小腹が空いたので、7丁目にあったLuke’s Lobsterという小さな店でロブスターロールを食べる。小さい見た目だったがロブスターの身が満載で、味付けも美味かった。
8丁目まで下りてきたので、夕方はチャイナタウン(Chinatown)まで歩くことにした。1丁目と1番街の交差点で標識の記念写真を撮った後、マンハッタン・ブリッジの入口に当たるキャナル・ストリート(Canal St.)まで7ブロックほど南下。グラマシーやイースト・ビレッジとはまた雰囲気ががらりと変わり、通りには漢字の看板がひしめく。この一角だけを切り取ればニューヨークとは思えない光景で、歩いて回れる距離に全く表情の異なる街が同居しているというマンハッタンの面白さを再認識するに至った。すぐ近くにはリトル・イタリー(Little Italy)という、もとはイタリアからの移民の街もある。ガイドブックに載っていたNha Trang Oneというベトナム料理店で、ヤウのソバ大を豪華にした感じのヌードルを食べる。安くて美味しい。
・マンハッタンヘンジ
帰りは、まずキャナル・ストリートからグランド・セントラルまで6号線で戻る。真のマンハッタンヘンジは今日の日没の予定なので、パーク・アベニューが高架になって42丁目をまたぐ地点へ。しかし行ってみると、路肩が巨大な群衆で溢れ返っていたのでとても撮れる状況ではない。そこで近くのストリートを色々と歩き回った末、駅の北側にある48丁目とパーク・アベニューの交差点で待ち構えることに決める。ところが、日が沈みゆくはずのニュージャージーの方角は完全に曇っているではないか。摩天楼の隙間は見事に雲海になっていて、今頃太陽はあの雲の向こう側で素晴らしい輝きを見せているのだろうと妄想しながら、撮影は見事に撃沈したのだった。昨日の実習後に撮っておいて正解であった。
写真
1枚目:『睡蓮』
2枚目:『ボールを持つ少女』
3枚目:ロブスターロール
2111文字
・MoMA(Museum of Modern Art)
今日はニューヨーク近代美術館、通称MoMAへ足を運ぶ。セントラルパークからさほど離れていないミッドタウン(Midtown)にある。学生証を見せたらどういうわけかタダ券をもらえたw 主に4階と5階の常設展を見て回る。モネの睡蓮、ゴッホの星月夜、それにリキテンスタイン(Lichtenstein)やウォーホル(Warhol)といった有名どころをチェックしながら歩を進める。いつもデュプロの「★」を拾いながら鑑賞するような形になるのは仕方ない。そういえば、星月夜に描かれた渦巻きはメニエール病の回転性めまいを表現したものだという説があるらしい。近代美術とあって全体的にかなり斬新な作品が多く、解説を聞くとさらに面白い。また格式ばった古典的な感じがなく、見ていても肩が凝らないとでも言えば良いのか、ごく自然な感覚で作品を鑑賞できるのが良かった。
しかし落書きにしか見えない絵や、全く訳の分からないオブジェもたくさんあって、たとえ意味付けがあっても一見して全く意味不明なものにどういう「意味」があるのか、という疑問は払拭されないままである。作品それ自体もさることながら、文脈まで含めた包括的なものに対しても目を向けないことには、これらは結局いつまでも分からない。してみると、いわゆる傑作が傑作たるゆえんは何なのかと、いつも不思議に思うわけだ。傑作という意見で多数が合意するから傑作たりえるのか、それとも絶対的な何かが内包されているのか。評価は他人が下すものなので、これはいつも難しい問題だと思っている。まあ、単に自分の勉強不足といえばそれまでかもしれない。
・散策
3時間弱の滞在の後、51丁目から23丁目まで6号線で移動。まずはグラマシー(Gramacy)を歩く。ガイドブックには歴史的建造物が多いとあったが、そこまで古い印象は受けない。壁のようなフラットアイアン・ビル(Flatiron Building)や、木陰にひっそりと佇むセオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)の生家を眺めつつ、ユニオン・スクエア(Union Square)まで南下する。4番街は歩行者天国になっていて、道路の両脇には無数の露店や屋台。この辺りまで来るとイースト・ビレッジ(East Village)という地区になり、色々な移民の街である。8丁目を東に歩くと日本の居酒屋やラーメン屋も散見される。小腹が空いたので、7丁目にあったLuke’s Lobsterという小さな店でロブスターロールを食べる。小さい見た目だったがロブスターの身が満載で、味付けも美味かった。
8丁目まで下りてきたので、夕方はチャイナタウン(Chinatown)まで歩くことにした。1丁目と1番街の交差点で標識の記念写真を撮った後、マンハッタン・ブリッジの入口に当たるキャナル・ストリート(Canal St.)まで7ブロックほど南下。グラマシーやイースト・ビレッジとはまた雰囲気ががらりと変わり、通りには漢字の看板がひしめく。この一角だけを切り取ればニューヨークとは思えない光景で、歩いて回れる距離に全く表情の異なる街が同居しているというマンハッタンの面白さを再認識するに至った。すぐ近くにはリトル・イタリー(Little Italy)という、もとはイタリアからの移民の街もある。ガイドブックに載っていたNha Trang Oneというベトナム料理店で、ヤウのソバ大を豪華にした感じのヌードルを食べる。安くて美味しい。
・マンハッタンヘンジ
帰りは、まずキャナル・ストリートからグランド・セントラルまで6号線で戻る。真のマンハッタンヘンジは今日の日没の予定なので、パーク・アベニューが高架になって42丁目をまたぐ地点へ。しかし行ってみると、路肩が巨大な群衆で溢れ返っていたのでとても撮れる状況ではない。そこで近くのストリートを色々と歩き回った末、駅の北側にある48丁目とパーク・アベニューの交差点で待ち構えることに決める。ところが、日が沈みゆくはずのニュージャージーの方角は完全に曇っているではないか。摩天楼の隙間は見事に雲海になっていて、今頃太陽はあの雲の向こう側で素晴らしい輝きを見せているのだろうと妄想しながら、撮影は見事に撃沈したのだった。昨日の実習後に撮っておいて正解であった。
写真
1枚目:『睡蓮』
2枚目:『ボールを持つ少女』
3枚目:ロブスターロール
2111文字
・進捗
同僚の留学生と色々話したのだが、どうもこの科は極めてvisiting student-unfriendlyだという結論に達した。当初は自分の英語力の問題なのか、積極性の問題なのか分かりかねていたのだが、これらの問題がそれなりに大きな比重を占めるのもさることながら、どうやら診療科の問題というのも見えてきた。アテンディングの面々は我々に話しかけることはおろか、目を合わせすらしない。むろん全てをそのせいにするわけでは毛頭ないのだが、このまま見ているだけというのはさすがに苦行なので、レジデントの長と思しき人物に食らいつき、病棟患者をフォローしてカルテを書くところまで何とかこぎつける。カルテは略語だらけで苦労したが、少しは慣れてきたか。あとは、コンサルの回診をカットして病棟のみに集中するという方針でも合意し、日々の疲労がずいぶん軽減されることとなった。
しかし、もし逆の立場だったらどうなのだろうと考えると、何とも言えない。右も左も分からない異邦人に構っている暇などないというのが実情なのだろう。前評判では「教育的」と聞いていたが、全てはケースバイケースの一言に尽きる。
・英語
徐々に速さにも慣れ、先週に比べれば多くの内容を聴解できるようになったが、話者の特性に依存する部分がまだ大きい。つまり、聴き取りやすい人とそうでない人に分かれる。それにしても、速い英語を聴くのは本当に疲れる。それは、ディクテーション→和訳というプロセスを同時並行で行っているからなのか。無意識ながら、日本語を介して内容を理解しようとする作用がはたらいてしまう。そのため、聴き取れない単語があるとそこで突然プロセスが停止し、全貌を見失う。一方、カンファでキーワードを板書してくれる場合は大変分かりやすい。脳内で聴解して文字に起こす作業、すなわちディクテーションの手間が一気に省けるからである。要はリスニングなのだ。
・マンハッタンヘンジ(Manhattanhenge)
当地の医学生から、今週はマンハッタンヘンジなる現象が見られると教えてもらう。これはストーンヘンジ(Stonehenge)にかけた造語で、日没の方角がちょうどマンハッタンのストリートが走る向きに一致する日が、夏至を等間隔に挟んで年に2度訪れるという。格子状道路をもつマンハッタンでは各ストリートは完全に平行に走っているので、任意のストリートに立って西の方角を見れば、両脇にそびえ立つ高層ビルの間にちょうど太陽が沈んでいくわけである。今年は7月12日(土)で、ニュージャージーの地平線に太陽が半分隠れるとき、ストリートに真っ直ぐ光が差し込む。一方、前日の11日(金)は少し北にずれて日が沈むのだが、太陽の下縁が地平線に接するときに、光線の向きと道路の走行が一致するらしい。
そういうわけで金曜の実習終了後は、34丁目とパーク・アベニューの交差点へ。日没間際になると道路はブルートレインの最終列車が出発するとき並みの大混雑で、群衆は往来を妨害して写真を撮りまくる。絶え間ない車のクラクションと歓声が入り混じる中、橙色に燃える太陽は鮮やかにビルの狭間へと沈んでいったのだった。
写真
1枚目:摩天楼の隙間へ
2枚目:落陽
3枚目:グランド・セントラル
1454文字
同僚の留学生と色々話したのだが、どうもこの科は極めてvisiting student-unfriendlyだという結論に達した。当初は自分の英語力の問題なのか、積極性の問題なのか分かりかねていたのだが、これらの問題がそれなりに大きな比重を占めるのもさることながら、どうやら診療科の問題というのも見えてきた。アテンディングの面々は我々に話しかけることはおろか、目を合わせすらしない。むろん全てをそのせいにするわけでは毛頭ないのだが、このまま見ているだけというのはさすがに苦行なので、レジデントの長と思しき人物に食らいつき、病棟患者をフォローしてカルテを書くところまで何とかこぎつける。カルテは略語だらけで苦労したが、少しは慣れてきたか。あとは、コンサルの回診をカットして病棟のみに集中するという方針でも合意し、日々の疲労がずいぶん軽減されることとなった。
しかし、もし逆の立場だったらどうなのだろうと考えると、何とも言えない。右も左も分からない異邦人に構っている暇などないというのが実情なのだろう。前評判では「教育的」と聞いていたが、全てはケースバイケースの一言に尽きる。
・英語
徐々に速さにも慣れ、先週に比べれば多くの内容を聴解できるようになったが、話者の特性に依存する部分がまだ大きい。つまり、聴き取りやすい人とそうでない人に分かれる。それにしても、速い英語を聴くのは本当に疲れる。それは、ディクテーション→和訳というプロセスを同時並行で行っているからなのか。無意識ながら、日本語を介して内容を理解しようとする作用がはたらいてしまう。そのため、聴き取れない単語があるとそこで突然プロセスが停止し、全貌を見失う。一方、カンファでキーワードを板書してくれる場合は大変分かりやすい。脳内で聴解して文字に起こす作業、すなわちディクテーションの手間が一気に省けるからである。要はリスニングなのだ。
・マンハッタンヘンジ(Manhattanhenge)
当地の医学生から、今週はマンハッタンヘンジなる現象が見られると教えてもらう。これはストーンヘンジ(Stonehenge)にかけた造語で、日没の方角がちょうどマンハッタンのストリートが走る向きに一致する日が、夏至を等間隔に挟んで年に2度訪れるという。格子状道路をもつマンハッタンでは各ストリートは完全に平行に走っているので、任意のストリートに立って西の方角を見れば、両脇にそびえ立つ高層ビルの間にちょうど太陽が沈んでいくわけである。今年は7月12日(土)で、ニュージャージーの地平線に太陽が半分隠れるとき、ストリートに真っ直ぐ光が差し込む。一方、前日の11日(金)は少し北にずれて日が沈むのだが、太陽の下縁が地平線に接するときに、光線の向きと道路の走行が一致するらしい。
そういうわけで金曜の実習終了後は、34丁目とパーク・アベニューの交差点へ。日没間際になると道路はブルートレインの最終列車が出発するとき並みの大混雑で、群衆は往来を妨害して写真を撮りまくる。絶え間ない車のクラクションと歓声が入り混じる中、橙色に燃える太陽は鮮やかにビルの狭間へと沈んでいったのだった。
写真
1枚目:摩天楼の隙間へ
2枚目:落陽
3枚目:グランド・セントラル
1454文字
M氏は、ミネアポリスへと帰って行った。これで、ニューヨークに一人である。木曜の朝から今朝までほぼぶっ通しで予定が入っていたので、さすがに疲弊した。再び部屋に戻って、昼過ぎまでぐだぐだと惰眠を貪る。午後は机に向かって日記を書いたりカルテを読んだりしてみるも、何となしに去来する虚しさに苛まれて今ひとつ捗らない。
・ブルックリン
何もせずに一日を過ごすのはもったいないので、夕方は116丁目、コロンビア大学近くの店で軽い夕食をとった後、マンハッタンの夜景がよく見えるというブルックリン・ブリッジ・パークへ足を運ぶことにした。地下鉄1号の緩行線と2・3号の急行線をタイムズ・スクエアで対面で乗り継ぎ、イースト・リバーをくぐった先のクラーク・ストリート(Clark St.)で下車。ここはダンボ(DUMBO: Down Under the Manhattan Bridge Overpass)と呼ばれる一帯にある。目当ての日没の時刻が近かったので街並みを見て回る時間はあまりなかったのだが、全体的に落ち着いた雰囲気で暮らしやすそうな場所である。沿岸にある公園までは駅から徒歩約10分。日曜とあってなかなか賑わっていた。自分と同じく三脚を携え夜景を撮りに来たと思われる人々も多数。
今日の日没は20時29分。残念なことに西の空だけ薄い雲がかかっているが、これはこれで味が出ている。20時40分頃、摩天楼の後ろに広がった雲が鮮やかな茜色に染まる。そして、21時過ぎまでの間は刻一刻と色彩が変化していく。地球の自転を感じるひと時とでも言えば良いのか、この天体は今まさに夜に入ろうとしているわけだ。同時に、ビルの窓にはぽつぽつと灯りがともり始める。空はますます暗くなっていく一方で、宝石のごとき人工の光はその煌めきを一段と増してゆく。やがて辺りがすっかり宵闇に包まれる頃、巨大戦艦のようなマンハッタンの姿がイースト・リバーの対岸に忽然と姿を現したのだった。
写真
1枚目:黄昏
2枚目:夜の始まり
3枚目:生まれ変わったワールド・トレード・センター(World Trade Center)
924文字
・ブルックリン
何もせずに一日を過ごすのはもったいないので、夕方は116丁目、コロンビア大学近くの店で軽い夕食をとった後、マンハッタンの夜景がよく見えるというブルックリン・ブリッジ・パークへ足を運ぶことにした。地下鉄1号の緩行線と2・3号の急行線をタイムズ・スクエアで対面で乗り継ぎ、イースト・リバーをくぐった先のクラーク・ストリート(Clark St.)で下車。ここはダンボ(DUMBO: Down Under the Manhattan Bridge Overpass)と呼ばれる一帯にある。目当ての日没の時刻が近かったので街並みを見て回る時間はあまりなかったのだが、全体的に落ち着いた雰囲気で暮らしやすそうな場所である。沿岸にある公園までは駅から徒歩約10分。日曜とあってなかなか賑わっていた。自分と同じく三脚を携え夜景を撮りに来たと思われる人々も多数。
今日の日没は20時29分。残念なことに西の空だけ薄い雲がかかっているが、これはこれで味が出ている。20時40分頃、摩天楼の後ろに広がった雲が鮮やかな茜色に染まる。そして、21時過ぎまでの間は刻一刻と色彩が変化していく。地球の自転を感じるひと時とでも言えば良いのか、この天体は今まさに夜に入ろうとしているわけだ。同時に、ビルの窓にはぽつぽつと灯りがともり始める。空はますます暗くなっていく一方で、宝石のごとき人工の光はその煌めきを一段と増してゆく。やがて辺りがすっかり宵闇に包まれる頃、巨大戦艦のようなマンハッタンの姿がイースト・リバーの対岸に忽然と姿を現したのだった。
写真
1枚目:黄昏
2枚目:夜の始まり
3枚目:生まれ変わったワールド・トレード・センター(World Trade Center)
924文字
U氏は、125丁目の交差点からタクシーに乗って空港へ。旅立ちを見届けた後、日中はH氏と共に市内を観光する。
・セントラルパーク
8時半に落ち合って、朝のセントラルパークを歩く。天候は快晴で心地良い。池のそばにあるレストハウスで軽い朝食をとる。整然と区画された大都市の中心にこれほど広大な公園があるというのはなかなか面白い。東京都心では、せいぜい新宿御苑くらいだろうか。
・メトロポリタン美術館
10時の開館に合わせて入る。まずは教科書通りの内容をということで、『地球の歩き方』に書いてあった「王道作品を半日で鑑賞」という安直なコースに乗っかって観覧する。何だかそれはそれで癪だが、ありがたいアドバイスには従った方が良いw ただ、これらを押さえるだけでもかなり歩き回らねばならず、改めてこの美術館の巨大さを感じる。モネ、マネ、ゴッホ、ゴーギャンあたりはやはり鉄板か。そういえばモネの絵しかない部屋もあった。この辺りの絵は素人にも大変理解しやすく、実にありがたい。
最近思うに、絵を見るときの観点が、写真を撮るときのそれに酷似してきた。同じ光景を写真に撮るとしたら、自分ならどうするだろうと空想するのはなかなか楽しい。あるいは、そもそもなぜその構図を切り取るに至ったのか、画家の思惑に踏み込んでみるのも一興である。絵も写真も、目にした光景と、それを処理した思考過程を有限空間の中に体現したものという点では大いに共通点があるのではないか。
・散策
土産物を買って美術館を出たらもう13時前になっていた。マディソン・アベニュー(Madison Ave.)沿いにあるカフェに入ってオムレツを食べる。その後はセントラルパークに戻って南限にあたる59丁目まで園内を通って行くことにする。一大ランドマークであるベセスダ(Bethesda)の噴水は、大勢の人で賑わっていた。しかしベセスダといえば、細胞診のクラス分類が真っ先に思い浮かぶのが悲しい。公園を出た後は、数々のブランドショップを横目に5番街を南下していく。巨大な銀座、表参道に相当するような通りだろうか。マンハッタンは場所によってまるで異なる街の顔になるから面白い。市立図書館前の木陰で少し休んだ後、タイムズ・スクエアへ。前回訪れたのは月曜だったが、今日は土曜ということで凄まじい混雑であった。
・ミュージカル
43丁目と8番街の交差点にあるスタバに入り、自由の女神をクルーズで見てきたというM氏と落ち合って3人になる。まだ辺りはかなり明るいが、今のうちに夕食をとっておこうということで、9番街にある適当なレストランに入った。その後、20時からはブロードウェイのミュージカルへ。観劇するのは『シカゴ(Chicago)』。49丁目にあるアンバサダー(Ambassador)劇場へ向かう。場内は意外にも狭かった。ここでも問題になるのはやはり英語で、筋を理解できたのは4割くらいだったか。急速なテンポで繰り広げられる会話とストーリーについていくのはなかなか難しいが、壮大なパフォーマンス、それに歌と音楽があるので雰囲気だけでも十分に楽しめる。いやしかし、よくあんなに歌ったり踊ったりできるものだ。
・エンパイア・ステート・ビル
劇場を出たのは22時半だったが、夜はまだ終わらない。人で溢れ返り、数々の電光掲示板が昼間のような明るさで煌めくタイムズ・スクエアを通り抜けた後、34丁目にあるエンパイア・ステート・ビルの展望台を目指した。
入口のエスカレーターで「2時間待ち」という不穏な言葉を耳にする。いや嘘だろうと思って階上へ行ってみると、そこにはディズニーランドのアトラクション待ちのような人の列がぐるぐると巻いている。既にチケットは確保してあったが、それでも相当に時間がかかりそうだ。エクスプレス・パスを持っていればエレベーターまですぐに到達できるようだが、この調子では確かに2時間くらいだろうか。しかしここまで来て諦めるのももったいないので、1時間あまりじっと粘ってようやく、80階へ行くエレベーターに乗ることができた。80階からは86階へ行くエレベーターに乗り換えねばならないのだが、ここでもさらに列が巻いていた。そろそろ絶望しかけていたところ、急遽係員が「階段で行きたい人は階段で行け」と言い出して、開放された階段室に全員が殺到。たまたま良い位置に並んでいたので、あっという間に86階の展望台に到着したのだった。アメリカ人のテキトーさはひどい。
しかし展望は絶景であった。如何せん混雑していたのであまりゆっくり滞在することはできなかったが、東にはクイーンズ(Queens)とブルックリン、南にはロウアー・マンハッタン(Lower Manhattan)の高層ビル群。西にはニュージャージー(New Jersey)の街、そして北には爆心地のように一際明るいタイムズ・スクエア。どの方角を見ても碁盤目状の街路が延々と展開し、その間を埋めるようにビルがぎっしりと建っている。ニューヨーク、マンハッタン島を鳥瞰しながら、夜が更けていった。
H氏をホテルまで送り、タクシーでihouseに戻ったのは2時頃であった。今宵はM氏が泊まる。
写真
1枚目:メトロポリタン美術館
2枚目:タイムズ・スクエア
3枚目:夜景
2349文字
・セントラルパーク
8時半に落ち合って、朝のセントラルパークを歩く。天候は快晴で心地良い。池のそばにあるレストハウスで軽い朝食をとる。整然と区画された大都市の中心にこれほど広大な公園があるというのはなかなか面白い。東京都心では、せいぜい新宿御苑くらいだろうか。
・メトロポリタン美術館
10時の開館に合わせて入る。まずは教科書通りの内容をということで、『地球の歩き方』に書いてあった「王道作品を半日で鑑賞」という安直なコースに乗っかって観覧する。何だかそれはそれで癪だが、ありがたいアドバイスには従った方が良いw ただ、これらを押さえるだけでもかなり歩き回らねばならず、改めてこの美術館の巨大さを感じる。モネ、マネ、ゴッホ、ゴーギャンあたりはやはり鉄板か。そういえばモネの絵しかない部屋もあった。この辺りの絵は素人にも大変理解しやすく、実にありがたい。
最近思うに、絵を見るときの観点が、写真を撮るときのそれに酷似してきた。同じ光景を写真に撮るとしたら、自分ならどうするだろうと空想するのはなかなか楽しい。あるいは、そもそもなぜその構図を切り取るに至ったのか、画家の思惑に踏み込んでみるのも一興である。絵も写真も、目にした光景と、それを処理した思考過程を有限空間の中に体現したものという点では大いに共通点があるのではないか。
・散策
土産物を買って美術館を出たらもう13時前になっていた。マディソン・アベニュー(Madison Ave.)沿いにあるカフェに入ってオムレツを食べる。その後はセントラルパークに戻って南限にあたる59丁目まで園内を通って行くことにする。一大ランドマークであるベセスダ(Bethesda)の噴水は、大勢の人で賑わっていた。しかしベセスダといえば、細胞診のクラス分類が真っ先に思い浮かぶのが悲しい。公園を出た後は、数々のブランドショップを横目に5番街を南下していく。巨大な銀座、表参道に相当するような通りだろうか。マンハッタンは場所によってまるで異なる街の顔になるから面白い。市立図書館前の木陰で少し休んだ後、タイムズ・スクエアへ。前回訪れたのは月曜だったが、今日は土曜ということで凄まじい混雑であった。
・ミュージカル
43丁目と8番街の交差点にあるスタバに入り、自由の女神をクルーズで見てきたというM氏と落ち合って3人になる。まだ辺りはかなり明るいが、今のうちに夕食をとっておこうということで、9番街にある適当なレストランに入った。その後、20時からはブロードウェイのミュージカルへ。観劇するのは『シカゴ(Chicago)』。49丁目にあるアンバサダー(Ambassador)劇場へ向かう。場内は意外にも狭かった。ここでも問題になるのはやはり英語で、筋を理解できたのは4割くらいだったか。急速なテンポで繰り広げられる会話とストーリーについていくのはなかなか難しいが、壮大なパフォーマンス、それに歌と音楽があるので雰囲気だけでも十分に楽しめる。いやしかし、よくあんなに歌ったり踊ったりできるものだ。
・エンパイア・ステート・ビル
劇場を出たのは22時半だったが、夜はまだ終わらない。人で溢れ返り、数々の電光掲示板が昼間のような明るさで煌めくタイムズ・スクエアを通り抜けた後、34丁目にあるエンパイア・ステート・ビルの展望台を目指した。
入口のエスカレーターで「2時間待ち」という不穏な言葉を耳にする。いや嘘だろうと思って階上へ行ってみると、そこにはディズニーランドのアトラクション待ちのような人の列がぐるぐると巻いている。既にチケットは確保してあったが、それでも相当に時間がかかりそうだ。エクスプレス・パスを持っていればエレベーターまですぐに到達できるようだが、この調子では確かに2時間くらいだろうか。しかしここまで来て諦めるのももったいないので、1時間あまりじっと粘ってようやく、80階へ行くエレベーターに乗ることができた。80階からは86階へ行くエレベーターに乗り換えねばならないのだが、ここでもさらに列が巻いていた。そろそろ絶望しかけていたところ、急遽係員が「階段で行きたい人は階段で行け」と言い出して、開放された階段室に全員が殺到。たまたま良い位置に並んでいたので、あっという間に86階の展望台に到着したのだった。アメリカ人のテキトーさはひどい。
しかし展望は絶景であった。如何せん混雑していたのであまりゆっくり滞在することはできなかったが、東にはクイーンズ(Queens)とブルックリン、南にはロウアー・マンハッタン(Lower Manhattan)の高層ビル群。西にはニュージャージー(New Jersey)の街、そして北には爆心地のように一際明るいタイムズ・スクエア。どの方角を見ても碁盤目状の街路が延々と展開し、その間を埋めるようにビルがぎっしりと建っている。ニューヨーク、マンハッタン島を鳥瞰しながら、夜が更けていった。
H氏をホテルまで送り、タクシーでihouseに戻ったのは2時頃であった。今宵はM氏が泊まる。
写真
1枚目:メトロポリタン美術館
2枚目:タイムズ・スクエア
3枚目:夜景
2349文字
・前夜
昨夜ボストン(Boston)からペン・ステーション(Penn Station)に到着した同級生U氏は、昨晩、今晩とihouseの居室に共に2泊する。さすがにベッドが狭すぎたが、何とか耐えた。いやしかし、男2人が密着して寝るというのも変な話であるw 同じくミネアポリス(Minneapolis)から飛んできたM氏は、Y氏宅へ行ったようだ。H氏は、セントラル・パーク(Central Park)からほど近いところに宿を取っているらしい。
・パーティー
独立記念日(Independence Day)の今日は、同じくアメリカに来ている同級生と共に、郊外で開かれる大先生のホームパーティーへ向かう。メトロノース・レールロード(Metro North Railroad)という近郊鉄道に乗ってマンハッタンから40マイルほど北東に離れたカトナ(Katonah)という駅へ。他の3人は始発のグランド・セントラルから乗っていたが、我々はその次のハーレム125丁目(Harlem-125th Street)駅から合流した。第三軌条から饋電される方式なので、架線や架線柱はない。列車は標準軌の線路を快調に飛ばしてゆくが、踏切に差しかかる度に警笛を何度も鳴らすのであまり落ち着かない。景色は次第に緑が深くなっていき、郊外に来たことを思わせる。
天気が雨だったのが唯一残念である。豪邸で開かれたパーティーは実に盛況なもので、ニューヨークで働いている日本人医師が多く参加していた。色々な話を聞くことができて興味深かったのだが、海外に暮らすということの意味を今一度深く考える機会になったかもしれない。この一か月間は、アメリカの医療現場や医学教育をよく観察して帰って来よう。
・酒宴
毎時1本の列車をタッチの差で逃してしまったこともあり、マンハッタンに戻ったら18時半であった。食料と酒を仕入れ、Y氏宅の屋上でささやかな酒宴が開かれる。今年はイースト・リバー(East River)から上がるという独立記念日の花火もここから見えるのではないかと思っていたのだが、打ち上げ場所ははるか南、マンハッタン・ブリッジとブルックリン・ブリッジの間だと分かったので、急いで外へ出て1番街を南下する。42丁目との交差点には人だかりができ始めていたので何かと思ったら、ビルの隙間から辛うじて花火を拝むことができたのだった。交通規制がかかっているわけでもないのに、今や交差点は人で溢れ返っている。花火が終わるまでは、車もその場に停まるしかない。
その後は部屋に戻って酒宴を再開。ihouseへ戻ったのは1時半頃であった。
写真
1枚目:メトロノース・レイルロード(これは客車列車だが、乗ったのは電車)
2枚目:花火
3枚目:グランド・セントラル
1258文字
昨夜ボストン(Boston)からペン・ステーション(Penn Station)に到着した同級生U氏は、昨晩、今晩とihouseの居室に共に2泊する。さすがにベッドが狭すぎたが、何とか耐えた。いやしかし、男2人が密着して寝るというのも変な話であるw 同じくミネアポリス(Minneapolis)から飛んできたM氏は、Y氏宅へ行ったようだ。H氏は、セントラル・パーク(Central Park)からほど近いところに宿を取っているらしい。
・パーティー
独立記念日(Independence Day)の今日は、同じくアメリカに来ている同級生と共に、郊外で開かれる大先生のホームパーティーへ向かう。メトロノース・レールロード(Metro North Railroad)という近郊鉄道に乗ってマンハッタンから40マイルほど北東に離れたカトナ(Katonah)という駅へ。他の3人は始発のグランド・セントラルから乗っていたが、我々はその次のハーレム125丁目(Harlem-125th Street)駅から合流した。第三軌条から饋電される方式なので、架線や架線柱はない。列車は標準軌の線路を快調に飛ばしてゆくが、踏切に差しかかる度に警笛を何度も鳴らすのであまり落ち着かない。景色は次第に緑が深くなっていき、郊外に来たことを思わせる。
天気が雨だったのが唯一残念である。豪邸で開かれたパーティーは実に盛況なもので、ニューヨークで働いている日本人医師が多く参加していた。色々な話を聞くことができて興味深かったのだが、海外に暮らすということの意味を今一度深く考える機会になったかもしれない。この一か月間は、アメリカの医療現場や医学教育をよく観察して帰って来よう。
・酒宴
毎時1本の列車をタッチの差で逃してしまったこともあり、マンハッタンに戻ったら18時半であった。食料と酒を仕入れ、Y氏宅の屋上でささやかな酒宴が開かれる。今年はイースト・リバー(East River)から上がるという独立記念日の花火もここから見えるのではないかと思っていたのだが、打ち上げ場所ははるか南、マンハッタン・ブリッジとブルックリン・ブリッジの間だと分かったので、急いで外へ出て1番街を南下する。42丁目との交差点には人だかりができ始めていたので何かと思ったら、ビルの隙間から辛うじて花火を拝むことができたのだった。交通規制がかかっているわけでもないのに、今や交差点は人で溢れ返っている。花火が終わるまでは、車もその場に停まるしかない。
その後は部屋に戻って酒宴を再開。ihouseへ戻ったのは1時半頃であった。
写真
1枚目:メトロノース・レイルロード(これは客車列車だが、乗ったのは電車)
2枚目:花火
3枚目:グランド・セントラル
1258文字
一日ごとにつけるのはやはり面倒なので、普段と同じように週区切りでまとめておく。
・体制
オリエンテーションもなく、スケジュールも何も分からないまま、唐突にスタート。7月の頭はスタッフの入れ替わりの時期で、新しいレジデントが入ってきたと見え、てんやわんやである。右も左も分からずついて回った中で、ようやく体制が把握できてきた。当科は病棟、小児のコンサル、新生児のコンサルを全て受け持っていて、回っているレジデントも神経内科、小児科、小児神経科がごちゃ混ぜになっている。毎朝8時から正午頃までアテンディングによる回診があり、各部門を順に回っていき、各レジデントが担当患者についてプレゼンする。小児科ポリクリの回診を毎日やっているに等しく、ほぼ立ちっぱなしで恐ろしくくたびれる。午後は、火曜が外来、水曜がカンファ、木曜が画像カンファとクルズス、といった風に色々な予定が入っている。外来は色々な患者がやって来て、いかにも日常診療といった風景を見ることができるので、面白い。スペイン語しか話さない患者が相当数いて、かなりの確率で通訳を要することに驚いた。
・英語
英語はあまりに速く、回診の内容は良くて3割くらいしか聞き取れない。脳外科医がやっていたクルズスに至っては1割くらいしか理解していなかったと思う。今まではヌルい英語を聴いて満足していたということか。まあこれは現場の生の英語なのだから、当たり前かもしれない。では、同じ内容が全部日本語だったらどうか。しかしポリクリの回診を冷静に振り返れば、音声としてのディクテーションはできても、その内容を10割理解しているわけではない。日本語の回診でも何を言わんとしているのかよく分からないことが多々あるのに、同じく高度に専門的な内容を外国語で討論するというのは極めて難しいことなのだと実感し、早々に壁にぶち当たったのだった。ただ3日間だけでも聴解はだいぶマシになったので、今後徐々に慣れていきたい。
・医学生
現在、自分よりもはるかにリスニングができていると見える韓国からの留学生と、当地の医学生の2人が一緒に回っている。驚くべきは当地の医学生の能力の高さで、レジデントと同等の仕事をバリバリこなしている様を見ると、日本のそこらの研修医よりもよっぽど診察技能や医学知識に長けているように思える。アメリカの医学教育はundergraduateの4年とmedical schoolの4年で合計8年、その最終学年にあたるとはいえ、同じ学生とは思えないレベルで驚嘆した。我々留学生の居場所はもはや見当たらない。しかし、当地の医学生が極めてフレンドリーなのが唯一の救いであった。
挫折感と無力感に襲われる初週。
写真
1枚目:国連本部
2枚目:エンパイア・ステート・ビル
3枚目:ブルックリン・ブリッジ
1271文字
・体制
オリエンテーションもなく、スケジュールも何も分からないまま、唐突にスタート。7月の頭はスタッフの入れ替わりの時期で、新しいレジデントが入ってきたと見え、てんやわんやである。右も左も分からずついて回った中で、ようやく体制が把握できてきた。当科は病棟、小児のコンサル、新生児のコンサルを全て受け持っていて、回っているレジデントも神経内科、小児科、小児神経科がごちゃ混ぜになっている。毎朝8時から正午頃までアテンディングによる回診があり、各部門を順に回っていき、各レジデントが担当患者についてプレゼンする。小児科ポリクリの回診を毎日やっているに等しく、ほぼ立ちっぱなしで恐ろしくくたびれる。午後は、火曜が外来、水曜がカンファ、木曜が画像カンファとクルズス、といった風に色々な予定が入っている。外来は色々な患者がやって来て、いかにも日常診療といった風景を見ることができるので、面白い。スペイン語しか話さない患者が相当数いて、かなりの確率で通訳を要することに驚いた。
・英語
英語はあまりに速く、回診の内容は良くて3割くらいしか聞き取れない。脳外科医がやっていたクルズスに至っては1割くらいしか理解していなかったと思う。今まではヌルい英語を聴いて満足していたということか。まあこれは現場の生の英語なのだから、当たり前かもしれない。では、同じ内容が全部日本語だったらどうか。しかしポリクリの回診を冷静に振り返れば、音声としてのディクテーションはできても、その内容を10割理解しているわけではない。日本語の回診でも何を言わんとしているのかよく分からないことが多々あるのに、同じく高度に専門的な内容を外国語で討論するというのは極めて難しいことなのだと実感し、早々に壁にぶち当たったのだった。ただ3日間だけでも聴解はだいぶマシになったので、今後徐々に慣れていきたい。
・医学生
現在、自分よりもはるかにリスニングができていると見える韓国からの留学生と、当地の医学生の2人が一緒に回っている。驚くべきは当地の医学生の能力の高さで、レジデントと同等の仕事をバリバリこなしている様を見ると、日本のそこらの研修医よりもよっぽど診察技能や医学知識に長けているように思える。アメリカの医学教育はundergraduateの4年とmedical schoolの4年で合計8年、その最終学年にあたるとはいえ、同じ学生とは思えないレベルで驚嘆した。我々留学生の居場所はもはや見当たらない。しかし、当地の医学生が極めてフレンドリーなのが唯一の救いであった。
挫折感と無力感に襲われる初週。
写真
1枚目:国連本部
2枚目:エンパイア・ステート・ビル
3枚目:ブルックリン・ブリッジ
1271文字
ついに6月が終わる。
・手続き
朝は少し出遅れてしまったが、168丁目にある医学部の事務へ行ってIDとパスワードをもらう。そして病院のカフェテリアで昼食をとった後、マスクのテストを行って諸々の手続きは完了。
・タイムズ・スクエア(Times Square)など
1号線を南下し、コロンブス・サークルで下車。予め頼んでおいた週末のミュージカルのチケットを回収する。その後、多少距離があったが白昼のブロードウェイを南下して「世界の中心の交差点」、タイムズ・スクエアまでてくてくと歩く。渋谷のスクランブル交差点をいくつかつなげたような感じである。平日の昼でもこれだけ混雑しているのだから、週末ともなると大変なことになるのだろう。しばらく写真撮影に興じた後、さらに34丁目まで歩いて東へ向かい、エンパイア・ステート・ビル(Empire State Building)を下から見上げる。パーク・アベニュー(Park Ave.)沿いに走る6号線に乗ってさらに南へ向かうことにした。
・ウォール(Wall)街など
ウォール・ストリート(Wall Street)で地下鉄を降り、ニューヨーク証券取引所とフェデラル・ホール(Federal Hall)を見る。道が狭いせいか日差しが届かず、思いのほか暗い通りであった。世界金融の中心地という雰囲気がしたかと言われるとそれは難しいところだが、マンハッタンでこれまで訪れたどの場所とも違う、ビジネス街のもつ独特の雰囲気が漂っていたように思う。その後はイースト・リバー(East River)沿いまで歩き、ようやく探し当てた見晴らしの良いデッキからブルックリン・ブリッジ(Brooklyn Bridge)を眺める。
・スタテンアイランド(Staten Island)フェリー
マンハッタンの南端から出る無料のフェリーに乗ると自由の女神(Statue of Liberty)が船上から見えるとのことだったので、乗船。所要は25分で、毎時4本ほど運航している。しかし下調べが甘く、夕方の時間帯は女神の顔がド逆光で撃沈した。シルエットはシルエットで絵になるのだが、滞在中に余裕があれば昼頃を狙ってもう一度来てみても良いか。代わりにマンハッタンの高層ビル群は陽光にきらめく姿がデッキからよく見えて、ちょっとしたクルーズ気分を味わえる。スタテンアイランドに到着後はターミナルの建物から外へ出ることもなく、同じ船でマンハッタンへとんぼ返りした。
元々あまり出歩く予定の一日ではなかったのだが、もう夜になってしまった。
写真
1枚目:Morgan Stanley Children’s Hospital of New York-Presbyterian (CHONY)
2枚目:タイムズ・スクエア
3枚目:自由の女神
1303文字
・手続き
朝は少し出遅れてしまったが、168丁目にある医学部の事務へ行ってIDとパスワードをもらう。そして病院のカフェテリアで昼食をとった後、マスクのテストを行って諸々の手続きは完了。
・タイムズ・スクエア(Times Square)など
1号線を南下し、コロンブス・サークルで下車。予め頼んでおいた週末のミュージカルのチケットを回収する。その後、多少距離があったが白昼のブロードウェイを南下して「世界の中心の交差点」、タイムズ・スクエアまでてくてくと歩く。渋谷のスクランブル交差点をいくつかつなげたような感じである。平日の昼でもこれだけ混雑しているのだから、週末ともなると大変なことになるのだろう。しばらく写真撮影に興じた後、さらに34丁目まで歩いて東へ向かい、エンパイア・ステート・ビル(Empire State Building)を下から見上げる。パーク・アベニュー(Park Ave.)沿いに走る6号線に乗ってさらに南へ向かうことにした。
・ウォール(Wall)街など
ウォール・ストリート(Wall Street)で地下鉄を降り、ニューヨーク証券取引所とフェデラル・ホール(Federal Hall)を見る。道が狭いせいか日差しが届かず、思いのほか暗い通りであった。世界金融の中心地という雰囲気がしたかと言われるとそれは難しいところだが、マンハッタンでこれまで訪れたどの場所とも違う、ビジネス街のもつ独特の雰囲気が漂っていたように思う。その後はイースト・リバー(East River)沿いまで歩き、ようやく探し当てた見晴らしの良いデッキからブルックリン・ブリッジ(Brooklyn Bridge)を眺める。
・スタテンアイランド(Staten Island)フェリー
マンハッタンの南端から出る無料のフェリーに乗ると自由の女神(Statue of Liberty)が船上から見えるとのことだったので、乗船。所要は25分で、毎時4本ほど運航している。しかし下調べが甘く、夕方の時間帯は女神の顔がド逆光で撃沈した。シルエットはシルエットで絵になるのだが、滞在中に余裕があれば昼頃を狙ってもう一度来てみても良いか。代わりにマンハッタンの高層ビル群は陽光にきらめく姿がデッキからよく見えて、ちょっとしたクルーズ気分を味わえる。スタテンアイランドに到着後はターミナルの建物から外へ出ることもなく、同じ船でマンハッタンへとんぼ返りした。
元々あまり出歩く予定の一日ではなかったのだが、もう夜になってしまった。
写真
1枚目:Morgan Stanley Children’s Hospital of New York-Presbyterian (CHONY)
2枚目:タイムズ・スクエア
3枚目:自由の女神
1303文字
9時半頃に起床。時差ボケはない。
・メトロポリタン(Metropolitan)美術館
再びY氏と観光へ出向く。まずはメトロポリタンへ。ここは相当に広大な美術館で、パリのルーヴル然り、とても1日で全てを見て回るのは無理である。王道のコースは来週に回すとして、今日は現代美術のコーナーを観覧した。しかしこの分野は解説がないと全く理解ができない。街中にある落書きを持ってきて館内に展示したのとどう違うのか、と言ってしまっては極論だが、結局展示されている場所と文脈で芸術の価値が決まっているのではないかと思ってしまう。そもそも、普遍的で本質的な意義が存在していることは誰も保証していないわけだ。
・昼食
日曜日で歩行者天国となっていたレキシントン・アベニュー(Lexington Ave.)をだらだらと南下して、54丁目と3番街の交差点近くにあるWolfgang’s Steakhouseへ入る。ガイドブックには「これぞアメリカン・ステーキ」と紹介されていたが、確かに美味かった。リブアイとハンバーグを分ける。
・グランド・セントラル(Grand Central)
10ブロックほど南下すれば、近郊路線のターミナル駅、グランド・セントラルに至る。内部は壮麗な建築で、海外大都市の中心駅にありがちなごみごみした感じがほとんどない。
・チェルシー(Chelsea)
昼下がりはダウンタウンへ。5番街の西側はチェルシーと呼ばれ、比較的閑静な雰囲気が漂う街である。ギャラリーがひしめいていることでも有名なようだが、日曜日なので残念ながらあまり多くは開いていなかった。ハドソン(Hudson)川の近くを南北に通るハイライン(The High Line)は貨物鉄道の高架廃線跡を緑地化した遊歩道で、休日は多くの人で賑わっている。道行く人は誰も気に留めないが、所々に見え隠れする往時の鉄路も良い味を出していた。しばらくここをぶらぶらと歩いた後、ミート・パッキング・ディストリクト(Meat Packing District)という、精肉工場の遺構を利用して誕生したショッピングモールへ行く。折角なので、海鮮市場でロブスターを食した。繊細という言葉からは程遠い、クルードな感じの美味さである。
・ソーホー(Soho)
夕方はさらに南下し、ソーホーへ。ここは買い物向きのエリアで、色々な店を適当に眺めただけで終了。1丁目よりも南にあるので、東西に走る通りには数字ではなく名前がついている。洒落た街並みと道路の幅員はパリのそれを彷彿させるものであった。歴史的な建築もいくつかあるようなので、次に来ることがあればそこも見ておきたい。
・夕食
国連本部近くにあるY氏宅に軽く立ち寄った後、2番街沿いにあるLa Cavaというワインバーで飲む。昼間にステーキとロブスターを食べたので、夜はつまみ程度で十分であった。渡米2日目にしてニューヨークを満喫したが、明後日からはいよいよ実習が控えている。見知らぬ土地を歩く楽しみとともに、緊張感と不安感が複雑に織り交ざった週末の夜である。
写真
1枚目:メトロポリタン美術館
2枚目:グランド・セントラル
3枚目:ハイライン
1522文字
・メトロポリタン(Metropolitan)美術館
再びY氏と観光へ出向く。まずはメトロポリタンへ。ここは相当に広大な美術館で、パリのルーヴル然り、とても1日で全てを見て回るのは無理である。王道のコースは来週に回すとして、今日は現代美術のコーナーを観覧した。しかしこの分野は解説がないと全く理解ができない。街中にある落書きを持ってきて館内に展示したのとどう違うのか、と言ってしまっては極論だが、結局展示されている場所と文脈で芸術の価値が決まっているのではないかと思ってしまう。そもそも、普遍的で本質的な意義が存在していることは誰も保証していないわけだ。
・昼食
日曜日で歩行者天国となっていたレキシントン・アベニュー(Lexington Ave.)をだらだらと南下して、54丁目と3番街の交差点近くにあるWolfgang’s Steakhouseへ入る。ガイドブックには「これぞアメリカン・ステーキ」と紹介されていたが、確かに美味かった。リブアイとハンバーグを分ける。
・グランド・セントラル(Grand Central)
10ブロックほど南下すれば、近郊路線のターミナル駅、グランド・セントラルに至る。内部は壮麗な建築で、海外大都市の中心駅にありがちなごみごみした感じがほとんどない。
・チェルシー(Chelsea)
昼下がりはダウンタウンへ。5番街の西側はチェルシーと呼ばれ、比較的閑静な雰囲気が漂う街である。ギャラリーがひしめいていることでも有名なようだが、日曜日なので残念ながらあまり多くは開いていなかった。ハドソン(Hudson)川の近くを南北に通るハイライン(The High Line)は貨物鉄道の高架廃線跡を緑地化した遊歩道で、休日は多くの人で賑わっている。道行く人は誰も気に留めないが、所々に見え隠れする往時の鉄路も良い味を出していた。しばらくここをぶらぶらと歩いた後、ミート・パッキング・ディストリクト(Meat Packing District)という、精肉工場の遺構を利用して誕生したショッピングモールへ行く。折角なので、海鮮市場でロブスターを食した。繊細という言葉からは程遠い、クルードな感じの美味さである。
・ソーホー(Soho)
夕方はさらに南下し、ソーホーへ。ここは買い物向きのエリアで、色々な店を適当に眺めただけで終了。1丁目よりも南にあるので、東西に走る通りには数字ではなく名前がついている。洒落た街並みと道路の幅員はパリのそれを彷彿させるものであった。歴史的な建築もいくつかあるようなので、次に来ることがあればそこも見ておきたい。
・夕食
国連本部近くにあるY氏宅に軽く立ち寄った後、2番街沿いにあるLa Cavaというワインバーで飲む。昼間にステーキとロブスターを食べたので、夜はつまみ程度で十分であった。渡米2日目にしてニューヨークを満喫したが、明後日からはいよいよ実習が控えている。見知らぬ土地を歩く楽しみとともに、緊張感と不安感が複雑に織り交ざった週末の夜である。
写真
1枚目:メトロポリタン美術館
2枚目:グランド・セントラル
3枚目:ハイライン
1522文字
・激烈行程
日本時間では翌日の朝6時頃だが、アドレナリンか何かの作用で目は冴えている。部屋を出発してD線の125丁目駅から161丁目のヤンキースタジアム(Yankee Stadium)へ向かう。ついこの間に実習を終えた同級生Y氏と、当地で知り合ったというその友人2人とでヤンキースとレッドソックスの試合を観に行くことになっているのだった。地下鉄は異常な混雑で、やむなく1本見送った。スタジアムは基本的に手ぶらで入らねばならないので、写真は携帯のカメラにて。ズームが全く効かないことを除けば、案外捨てたものではない。
・観戦
そもそも普段から野球を観ることもなければ、ましてナマで観戦したこともない。ルールは一応知っている、という程度のニワカ野郎が、田中将大の先発するレッドソックス戦を観に来たわけである。3回にソロホームランを食らって先制されるも、4回にショートのエラーで1点を巻き返す。しかし9回に2アウト2ストライクでソロを被弾し、ヤンキースは敢え無く敗北となった。マーくん良く投げていたと思うんだが。レッドソックスは9回に上原が登場し、代打イチローとの対決があったのがこの試合のもう一つの見どころだったが、1球目でセンターライナーに終わっていた。
ヤンキース打線がショボかった以外、初観戦にしては十分すぎるくらいの充実した試合。ビールを片手にジャンクフードを食べながら、暮れなずむ広大な球場に身を置くのは実に心地よい。また大画面や音響の演出も派手で面白く、ニワカ野郎フレンドリーな内容だった。両チームの選手のプロフィールとか戦略的な面をもっと深く知れば、観戦の楽しさはきっと今回の比ではないのだろう。野球にハマっている人は、そういう部分を熟知しているのだと思う。
・家路
同じ道を引き返す。D線の125丁目からブロードウェイ(Broadway)までの間はハーレム(Harlem)の地区を歩くことになるのだが、なかなか油断ならない空気が漂う。人通りの少ないモンマルトルといった感じか。125丁目はメインストリートなので全く安全な方だが、もっと北西の地区で興味本位で小道に入るのは本当に避けた方が良いらしい。
深い眠りに就く。
写真
1枚目:ヤンキースタジアム
2枚目:グレートホール
3枚目:観戦
1057文字
日本時間では翌日の朝6時頃だが、アドレナリンか何かの作用で目は冴えている。部屋を出発してD線の125丁目駅から161丁目のヤンキースタジアム(Yankee Stadium)へ向かう。ついこの間に実習を終えた同級生Y氏と、当地で知り合ったというその友人2人とでヤンキースとレッドソックスの試合を観に行くことになっているのだった。地下鉄は異常な混雑で、やむなく1本見送った。スタジアムは基本的に手ぶらで入らねばならないので、写真は携帯のカメラにて。ズームが全く効かないことを除けば、案外捨てたものではない。
・観戦
そもそも普段から野球を観ることもなければ、ましてナマで観戦したこともない。ルールは一応知っている、という程度のニワカ野郎が、田中将大の先発するレッドソックス戦を観に来たわけである。3回にソロホームランを食らって先制されるも、4回にショートのエラーで1点を巻き返す。しかし9回に2アウト2ストライクでソロを被弾し、ヤンキースは敢え無く敗北となった。マーくん良く投げていたと思うんだが。レッドソックスは9回に上原が登場し、代打イチローとの対決があったのがこの試合のもう一つの見どころだったが、1球目でセンターライナーに終わっていた。
ヤンキース打線がショボかった以外、初観戦にしては十分すぎるくらいの充実した試合。ビールを片手にジャンクフードを食べながら、暮れなずむ広大な球場に身を置くのは実に心地よい。また大画面や音響の演出も派手で面白く、ニワカ野郎フレンドリーな内容だった。両チームの選手のプロフィールとか戦略的な面をもっと深く知れば、観戦の楽しさはきっと今回の比ではないのだろう。野球にハマっている人は、そういう部分を熟知しているのだと思う。
・家路
同じ道を引き返す。D線の125丁目からブロードウェイ(Broadway)までの間はハーレム(Harlem)の地区を歩くことになるのだが、なかなか油断ならない空気が漂う。人通りの少ないモンマルトルといった感じか。125丁目はメインストリートなので全く安全な方だが、もっと北西の地区で興味本位で小道に入るのは本当に避けた方が良いらしい。
深い眠りに就く。
写真
1枚目:ヤンキースタジアム
2枚目:グレートホール
3枚目:観戦
1057文字
どういう形式で日記をつけるか思案したが、これがなかなか難しい。とりあえず平日の実習については、簡単な記録文と感想文を綴るに留めておく。ポリクリ同様、あまり詳細に書きすぎるのも問題なので、帰国後に提出する報告書を作る際の備忘録となれば良いか。そして週末の観光については、いつもの旅行記のような分量では大変だから、これも省力気味に済ませるとしよう。何時に何線に乗ったとかの詳細な行程をいちいちフォローするのは困難を極めるw
成田を11時に発つ全日空10便でニューヨーク(New York)へ。13時間弱のフライト。機内ではほとんど眠れず、同日、ほぼ同時刻の異国の地に降り立った。初のアメリカ大陸。空港からマンハッタン(Manhattan)への交通手段はいくつかあるが、エアトレイン(Air Train)と地下鉄A線を乗り継ぐという最も安価なルートを選ぶ。
地下鉄は相当に汚い。ブルックリン(Brooklyn)を走っている間の沿線風景はいかにも治安の悪そうな感じで、車内も険悪で殺伐とした空気である。59丁目のコロンブス・サークル(Columbus Circle)で1号線に乗り換え、125丁目で下車。入国審査と税関を通過してからほぼ2時間を要した。そして重いスーツケースを引きずりながら坂道を登り、14時、I-House(International House)に到着。今夜から37晩泊まることになる場所である。
残念ながら部屋にエアコンはないので、窓を開けて天井扇を回す。ほどよい涼しさである。ニューヨークの7月は暑くなるだろうが、エアコンを自前で用意して設置するのはあまりに面倒なので、この環境で耐え忍ぶとしよう。備品をチェックして、荷解きを終えて、ようやく一息つく。時計を見ると、もう17時になっている。
写真
1枚目:空港
2枚目:居室
776文字
成田を11時に発つ全日空10便でニューヨーク(New York)へ。13時間弱のフライト。機内ではほとんど眠れず、同日、ほぼ同時刻の異国の地に降り立った。初のアメリカ大陸。空港からマンハッタン(Manhattan)への交通手段はいくつかあるが、エアトレイン(Air Train)と地下鉄A線を乗り継ぐという最も安価なルートを選ぶ。
地下鉄は相当に汚い。ブルックリン(Brooklyn)を走っている間の沿線風景はいかにも治安の悪そうな感じで、車内も険悪で殺伐とした空気である。59丁目のコロンブス・サークル(Columbus Circle)で1号線に乗り換え、125丁目で下車。入国審査と税関を通過してからほぼ2時間を要した。そして重いスーツケースを引きずりながら坂道を登り、14時、I-House(International House)に到着。今夜から37晩泊まることになる場所である。
残念ながら部屋にエアコンはないので、窓を開けて天井扇を回す。ほどよい涼しさである。ニューヨークの7月は暑くなるだろうが、エアコンを自前で用意して設置するのはあまりに面倒なので、この環境で耐え忍ぶとしよう。備品をチェックして、荷解きを終えて、ようやく一息つく。時計を見ると、もう17時になっている。
写真
1枚目:空港
2枚目:居室
776文字
・準備
本来のスケジュールなら放射線科だが、年度の初っ端に済ませてしまった。今週もまるまる空いている。そのような時間を上手に使うのはなかなか難しいのだが、とりあえずストイックに教科書を読み、付け焼刃的に春休みのPreparation Courseの復習をして、Dr. Houseのシーズン1も全て観終える。向こうで役立ちそうな資料も揃え、ひとまず「万全の」装備はできたか。まあ装備と能力は別のものなので、あとはどれだけ自分が通用するのかということになる。そういえばマッチングも直前までドタバタで果たしてどうなるかと思ったが、滑り込みでセーフ。相変わらず履歴書を作るのには神経を使う。あとは、帰国時に空港の郵便局から郵送する一件を残すのみとなった。
・同窓会
月曜は、3年前のWritingクラスのささやかな集まり。しかし、あれから3年も経ったのか。当時はまだ薬理とか寄生虫とかをやっていたわけだが、にわかには信じがたい。
・壮行会
有難いことに、こんな会を開いて頂いた。木曜は四谷三丁目で美酒に浸る。
代々木ともしばしの別れ。細々した追加の買出しも済ませ、荷造りも終了。いよいよか。
写真:特急サンライズ出雲車内
中国旅行の連載写真は今日でおしまい。明日からは、できるだけリアルタイムで現地から更新してみようと思います。
698文字
本来のスケジュールなら放射線科だが、年度の初っ端に済ませてしまった。今週もまるまる空いている。そのような時間を上手に使うのはなかなか難しいのだが、とりあえずストイックに教科書を読み、付け焼刃的に春休みのPreparation Courseの復習をして、Dr. Houseのシーズン1も全て観終える。向こうで役立ちそうな資料も揃え、ひとまず「万全の」装備はできたか。まあ装備と能力は別のものなので、あとはどれだけ自分が通用するのかということになる。そういえばマッチングも直前までドタバタで果たしてどうなるかと思ったが、滑り込みでセーフ。相変わらず履歴書を作るのには神経を使う。あとは、帰国時に空港の郵便局から郵送する一件を残すのみとなった。
・同窓会
月曜は、3年前のWritingクラスのささやかな集まり。しかし、あれから3年も経ったのか。当時はまだ薬理とか寄生虫とかをやっていたわけだが、にわかには信じがたい。
・壮行会
有難いことに、こんな会を開いて頂いた。木曜は四谷三丁目で美酒に浸る。
代々木ともしばしの別れ。細々した追加の買出しも済ませ、荷造りも終了。いよいよか。
写真:特急サンライズ出雲車内
中国旅行の連載写真は今日でおしまい。明日からは、できるだけリアルタイムで現地から更新してみようと思います。
698文字